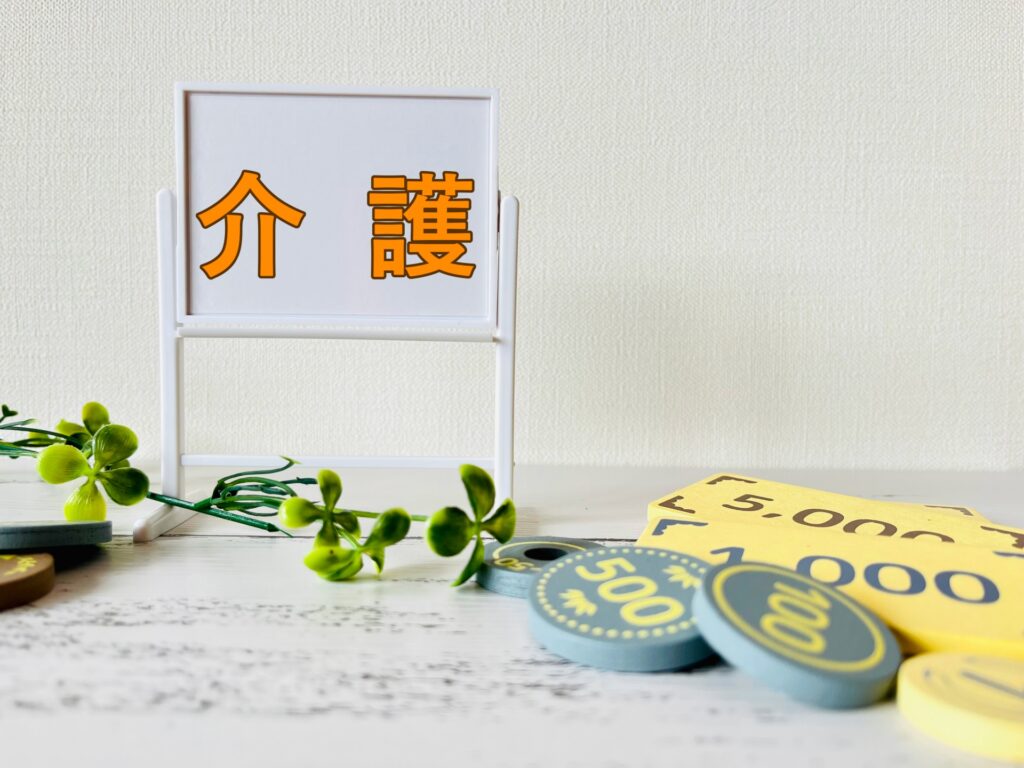2024年(令和6年)度に実施される介護報酬改定について、今回は居宅介護支援における「特定事業所加算」を中心に大幅な見直しが行われています。この改定は、多様化・複雑化する介護の現場に対応し、業務の効率化や連携強化を図ることを目的としています。本記事では、改定の背景や具体的な変更点及びこれまでに発出されたQ&Aについて詳しく解説します。
見直しの観点
・多様化・複雑化する課題に対応する取り組みの促進
・人材の有効活用
・他のサービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上
居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
ア 兼務に関する要件の明確化
今回の改定では、居宅介護支援事業者が「介護予防支援」や「地域包括支援センターの委託事業」を行う場合の兼務に関して、より明確なルールが追加されました。
具体的には、
「(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の(主任)介護支援専門員を配置していること。」に加えて、「利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。」という文言が追記されております。
この変更により、事業所内での役割の柔軟性が高まり、効率的な業務運営が可能となります。
イ 新たな算定要件の追加
介護の現場で多様化・複雑化する課題に対応するため、新たな算定要件が導入されました。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
「(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」
この要件は、多様なニーズに対応できる専門性の向上を目的としており、地域社会における幅広い支援を促進します。
ウ 運営基準減算に関する改正
事業所の管理負担軽減のため、運営基準減算に関する規定が改正されました。従来の規定では、運営基準減算を受けている事業所は特定事業所加算を受けられませんでしたが、今回の改定により、運営基準減算の適用を受けていても特定事業所加算が算定できることになりました。これにより、事業所の毎月の確認作業の負担が軽減され、加算の適用範囲が広がりました。
1人当たりの取り扱い件数の見直し
ア 報酬規定上の取り扱い
今回の報酬改定では、ケアマネジメントの質を確保しながらも業務効率化を進めることで、介護支援専門員の人材を有効活用する目的で、1人当たりの取り扱い件数が以下のように変更となりました。
● 居宅介護支援費(Ⅰ)
居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)40未満⇒45未満
居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)40以上60未満⇒45以上60未満
● 居宅介護支援費(Ⅱ)
居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、「ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合」に改められました。
居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)「45 未満」⇒「50 未満」
居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)「45 以上 60 未満」⇒「50 以上 60 未満」
● 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出について
居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて得た数を件数に加えることとされました。
イ 運営規定上の取り扱い
指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準についても見直されております。
●原則 、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が 44 又はその端数を増すごとに1とする 。
1~44人 1人
45人~88人 2人
89~ 132人 3人
●居宅介護支援事業者と居宅サービス事業者等との間において、「ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合」においては、要介護者の数に要支援者の数に 3分の1を乗じた数を加えた数が 49 又はその端数を増すごとに1と見直されました。
1~49人 1人
50人~98人 2人
99~ 147人 3人
他の居宅サービス事業所との連携によるモニタリング
人材の有効活用、居宅サービス事業者等との連携促進の観点から、以下の要件で、テレビ電話装置その他の通信機器を活用したモニタリングが可能となりました。
ア 利用者の同意を得ること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者など関係者の合意を得ていること。
●利用者の状態が安定していること。
●利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
●テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。
ウ 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。
居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援を行う場合の取り扱い
ア 市町村長に対し、情報提供することを運営基準上義務付けることに伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設けることとされました。
<現行>
介護予防支援費 438単位
↓
<改定後>
介護予防支援費(Ⅰ) 442単位 ※地域包括支援センターのみ
介護予防支援費(Ⅱ) 472単位(新設)※指定居宅介護支援事業者のみ
イ 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。
※介護予防支援費(Ⅱ)のみ
特別地域介護予防支援加算 所定単位数の15%を加算(新設)
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算(新設)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算(新設)
ウ 以下の通り、運営基準についても見直しが行われました。
●居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。
●管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がないときに限る。)には兼務を可能とする。
まとめ
令和6年度の介護保険報酬改定では、介護の現場で多様化・複雑化する課題への対応に加え、テクノロジーの導入促進や業務効率化に向けた取り組みを踏まえた、居宅介護支援事業所にとって重要な変更がいくつか導入されております。これらの改定内容をしっかりと把握し、今後の運営に活かしていくことが望まれます。
次に、これまで発出されたQ&Aをご紹介します。
Q&A VOL.1
問106 テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、訪問介護員が訪問している間に、テレビ電話装置等の準備をすることは可能か。
(答)
訪問介護の提供に支障が生じない範囲で、例えば ICT 機器の On/Off 等の協力などを行うことは差し支えないが、具体的な実施方法や連携方法等は、あらかじめ指定居宅介護支援事業所と訪問介護事業所とで調整すること。また、協力・連携の範囲について、利用者の要望や目的によっては、適切ではない場合等もあると考えられるため、その必要性等については、状況に応じて判断する必要がある。
問107 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成後、初回のモニタリングについてもテレビ電話装置等を活用して行うことは可能か。
(答)
要件を満たしていれば可能であるが、居宅サービス計画等の実施状況を適切に把握する観点から、初回のモニタリングは利用者の居宅を訪問して行い、その結果を踏まえた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが可能かどうかを検討することが望ましい。
問108 情報連携シートの項目はすべて記載する必要があるか。
(答)
テレビ電話装置等を活用したモニタリングのみでは収集できない情報について、居宅サービス事業者等に情報収集を依頼する項目のみを記載すればよい。
問109 サービス事業所に情報収集を依頼するにあたり、情報連携シートではなく、民間の介護ソフト・アプリの記録機能を活用する方法は認められるか。
(答)
情報連携シートは様式例であるため、必ずしもこの様式に限定されないが、介護ソフト・アプリの記録機能を活用する場合においても、情報連携シートの項目と照らし、指定居宅介護支援事業者と居宅サービス事業者等の連携に必要な情報が得られるかを確認すること。
問110 利用者に特段の事情がある場合には1月に1回(介護予防支援の場合は3月に1回)のモニタリングを行わなくてもよいが、利用者が使用するテレビ電話装置等のトラブルによりモニタリングが実施できなかった場合は特段の事情に該当するか。
(答)
該当しない。この場合は、利用者の居宅への訪問によるモニタリングに切り替えること。
問111 文書により利用者の同意を得る必要があるが、重要事項説明書等にチェック欄を設けるなどの対応でも差し支えないか。
(答)
利用者やその家族に対し、テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、そのメリット・デメリットを含め十分に説明した上で、チェック欄にチェックを入れることにより同意を得ることは差し支えない。
問114 利用者数が介護支援専門員1人当たり 45 件以上の場合における居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)又は居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ)の割り当てについて具体的に示されたい。
(答)
【例1】
取扱件数80人で常勤換算方法で1.6人の介護支援専門員がいる場合
① 45(件)×1.6(人)=72(人)
② 72(人)-1(人)=71(人)であることから、
1件目から71件目については、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)を算定し、72件目から
80件目については、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)を算定する。
【例2】
取扱件数160人で常勤換算方法で2.5人介護支援専門員がいる場合
① 45(件)×2.5(人)=112.5(人)
② 端数を切り捨てて112(人)であることから、
1件目から112件目については、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)を算定する。
113件目以降については、
③ 60(件)×2.5(人)=150(人)
④ 150(人)-1(人)=149(人)であることから、
113件目から149件目については居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)を算定し、150件
目から160件までは、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ)を算定する。
○ 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件
問 115 事務職員の配置にあたっての当該事業所の介護支援専門員が行う基準(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)第 13 条に掲げる一連の業務等について具体例を示されたい。
(答)
基準第 13 条に掲げる一連の業務等については、基準第 13 条で定める介護支援専門員が行う直接的なケアマネジメント業務の他に、例えば、以下のような間接的なケアマネジメント業務も対象とする。
<例>
○ 要介護認定調査関連書類関連業務
・ 書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど
○ ケアプラン作成関連業務
・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど
○ 給付管理関連業務
・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど
○ 利用者や家族との連絡調整に関する業務
○ 事業所との連絡調整、書類発送等業務
○ 保険者との連絡調整、手続きに関する業務
○ 給与計算に関する業務 等
問121 市町村が指定介護予防支援事業者の指定に係る条例を定めるに当たり、指定を受けられる事業者の要件を独自に設けることは可能か。
(答)
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準のうち、基準第1条第3号及び第4号に規定する「市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準」以外のものについては、「市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準」とされているため、当該基準を参酌した上で、独自の要件を設けることは可能である。
問122 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の附則の規定により、令和9年3月 31 日までの間は、引き続き、令和3年3月 31 日における管理者である介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く)を管理者とすることができるとされているが、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、上記の介護支援専門員を管理者とすることは可能か。
(答)
原則不可だが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
問123 介護予防支援の指定を受けている指定居宅介護支援事業者が、地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けることは可能か。
(答)
・ 可能である。
・ 介護予防支援の指定は、介護予防支援の提供を受ける被保険者の保険者ごとに指定を受ける必要があるため、例えば、指定を受けていない保険者の管轄内に居住する被保険者に対し介護予防支援を提供する場合には、当該保険者の管轄する地域包括支援センターからの委託を受ける場合が考えられる。
Q&A VOL.3
問5 テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月において、サービス利用票
(控)に利用者の確認を受ける方法としてどのようなものが考えられるか。
(答)
訪問によるモニタリングを行う月において、直後のテレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月の分もサービス利用票(控)を持参し確認を受ける方法や、電子メール等により確認を受ける方法等が考えられる。
問6 指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を提供していた利用者について、要介護認定を受け、引き続き当該事業所が居宅介護支援を提供する場合において、初回加算の算定は可能か。
(答)
指定介護予防支援事業所の利用実績は問わないため、算定できる(介護予防支援費の算定時においても同様である)。
問7 居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防サービス計画を作成していた利用者について、当該居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受け、当該利用者に対し直接介護予防支援を提供する場合、初回加算を算定できるのか。
(答)
算定可能である。なお、初回加算は指定介護予防支援事業者として新規で介護予防サービス計画を作成する手間を評価するものであるため、お尋ねの事例においては、原則として改めてアセスメント等を行った上で介護予防サービス計画を作成する必要がある。
今回の見直しに伴い、公表されているQ&Aは以上です。
↓