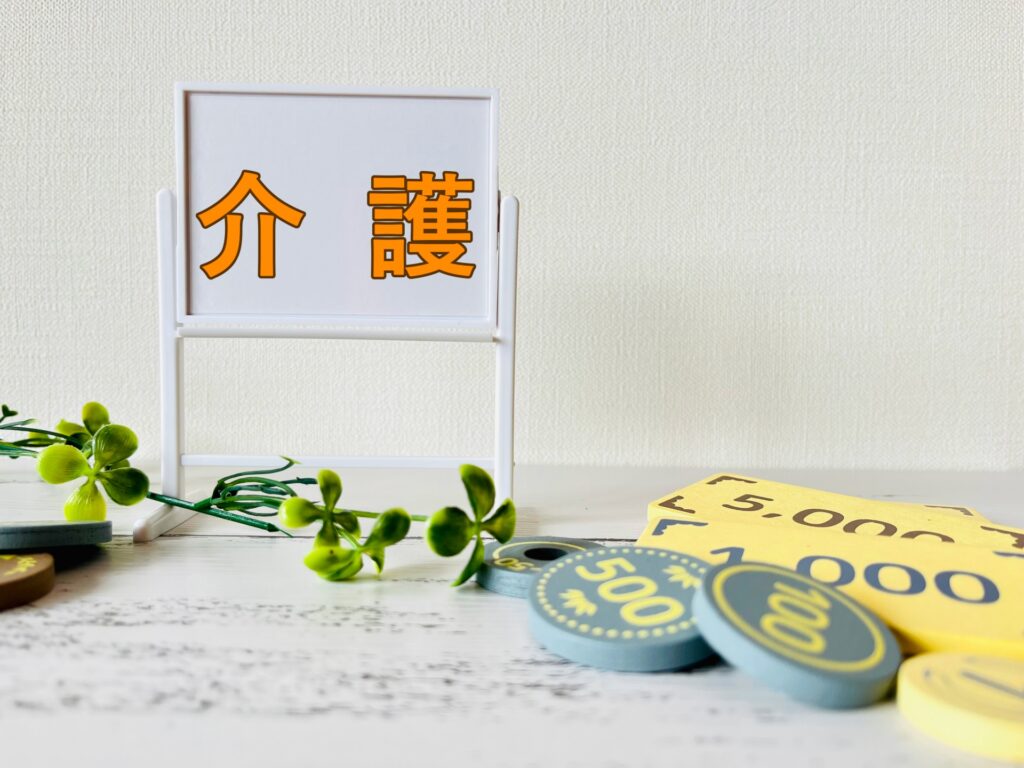慢性疾患や複数の疾患を抱える患者、医療・介護の複合ニーズを有する患者・利用者が増加しており、医療の視点を踏まえたケアマネジメント、医療ニーズが高い方へのサービス提供を強化する必要がある一方で、介護保険事業者は看取りへの対応も求められております。以下に、今回見直しが行われた看取りへの取り組みメニューについてご紹介します。
1 訪問入浴介護における看取り対応体制の評価について
【訪問入浴介護】
約6割の訪問入浴介護事業所が看取り期の利用者に対してサービスを提供していますが、利用者の身体状態に特に注意を払う必要があるため、時間がかかることも多く、事業所側の体制も通常とは変えなければならない場面も多くあります。また、医師や訪問看護師などの多職種との連携が不可欠で、現場では複雑な対応が求められています。
しかし、これまでの訪問入浴介護では、看取り期の利用者に対する特別な評価は行われていませんでした。こうした実態を踏まえ、今回の制度改定では、訪問入浴介護事業所が看取り期の利用者に適切に対応できるよう、新たな「看取り連携体制加算」が設けられました。この加算は、医療職や訪問看護ステーションと緊密に連携し、利用者の状況に応じた適切なサービス提供を評価するものです。
改定内容
現行: 看取り期に対する特別な加算はなし
改定後: 看取り連携体制加算(64単位/回、新設)
※死亡日及び死亡日以前30日以下に限る。
利用者基準
・医師が医学的知見に基づいて回復の見込みがないと診断した者であること。
・看取り期における対応方針に基づき、介護職員や看護職員から説明を受け、同意した上でサービスを受けていること。家族も同様に説明を受け、同意していること
事業所基準
・訪問看護ステーションなどとの連携体制が整備されており、必要に応じて訪問看護が提供されるよう調整が行われていること。
・看取り期における対応方針を定め、利用開始時に利用者や家族に対してその方針を説明し、同意を得ていること。
・看取りに関する職員研修を実施していること。
この新たな加算制度により、訪問入浴介護事業所は、看取り期の利用者に対してさらに質の高いケアを提供できるようになり、医療職との連携が強化されることで、利用者と家族にとって安心できるサービスの提供が期待されます。
2 訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し
【訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護】
看取り期では通常のケアに加えて、入浴前後では「身体の保全行為(褥瘡保護や防水処理など)」や「創傷へのスキンケア」が多く見られ、入浴中では「呼吸状態や意識状態の観察」が増えています。
これらのケア内容を踏まえ、ターミナルケア加算の見直しが行われました。評価の向上が図られています。
改定内容
現行: ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月
改定後: ターミナルケア加算 2,500単位/死亡月
3 短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
短期入所生活介護においても、看取り期の利用者へのサービス提供体制の強化が求められています。短期入所における看取り期の利用者に対するケアを行う際には看護職員の体制確保を評価するために、新たに「看取り連携体制加算」が設けられました。
改定内容
現行: 加算なし
改定後: 看取り連携体制加算 64単位/日(新設)
対象は死亡日および死亡日の30日前までで、7日を限度とする
算定要件
○次のいずれかに該当すること
- 看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)イ・ロを算定していること、
- 看護体制加算(Ⅰ)または(Ⅲ)イ・ロを算定し、短期入所生活介護事業所の看護職員や病院・診療所等と24時間連携できる体制を確保していること。
○看取り期における対応方針を定め、利用者やその家族に説明し、同意を得ていること。
4 ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
【居宅介護支援】
近年、終末期ケアにおいて、自宅で最期を迎えたいと考える利用者が増えています。そのような利用者の意向を尊重し、人生の最終段階における意思を適切に把握することが重要視されています。これを受けて、ターミナルケアマネジメント加算の対象となる疾患が、これまでの「末期の悪性腫瘍」だけに限られず、医師が一般的に認められた医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断された場合も対象となるよう見直しが行われました。
特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数についても見直しが行われ、今後さらに質の高い連携が求められるようになります。
改定内容
<現行>
在宅で死亡した利用者が「末期の悪性腫瘍の患者」に限り、その死亡日および死亡日前14日以内に2日以上訪問し、利用者や家族の同意を得た上で心身の状況を記録し、主治医や居宅サービス事業者に提供した場合に加算。
<改定後>
対象疾患を末期の悪性腫瘍に限らず、回復見込みがないと診断された場合も対象に拡大。在宅で死亡した利用者に対し、終末期の医療やケア方針に関する意向を把握し、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上訪問して同様のサービスを提供した場合に加算対象となる。
特定事業所医療介護連携加算の変更点
<現行>
前々年度の3月から前年度の2月までの間にターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していることが要件。
<改定後>
前々年度の3月から前年度の2月までにターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していることが要件に変更。なお、令和7年3月31日までは従前の例による経過措置が適用され、段階的な変更が行われる。
5 介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し
【介護老人保健施設】
介護老人保健施設(老健)の看取りに対する対応が大きく見直されることとなりました。超強化型や強化型の施設では、基本型と比較して、利用者の死亡日が近づいてから入所し、看取りが行われる割合が高い傾向があります。
老健施設では、終末期の利用者に対して手厚い医療対応が行われる一方で、医療費が基本報酬に含まれているため、これらの医療コストが施設の持ち出しとなってしまう現状があります。こうした状況を改善し、施設での看取り対応を充実させるために、今回の見直しが行われました。
特に、在宅復帰や在宅療養支援を行う老健施設において、ターミナルケア加算が適切に評価されるよう、死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価が見直され、死亡日やその前日に重点を置いた新しい加算体系が導入されます。
改定内容
<現行>
死亡日45日前~31日前:80単位/日
死亡日30日前~4日前:160単位/日
死亡日前々日、前日:820単位/日
死亡日:1,650単位/日
<改定後>
死亡日45日前~31日前:72単位/日(変更)
死亡日30日前~4日前:160単位/日(変更なし)
死亡日前々日、前日:910単位/日(変更)
死亡日:1,900単位/日(変更)
これにより、死亡日やその前後における手厚い対応がより適切に評価され、施設側の医療コストの負担が軽減されることが期待されます。
算定要件
・医師が医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断された入所者であること。
・入所者またはその家族の同意を得て、ターミナルケアに関する計画が作成されていること。
・医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士などが協力して、入所者の状態や家族の求めに応じて説明を行い、同意を得た上でターミナルケアが行われていること。
※「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省)」等の内容に沿った取組を行うことが重要とされております。
この見直しによって、老健施設におけるターミナルケアの質がさらに向上し、利用者とその家族にとって、より安心して看取りのケアが受けられる環境が整えられることが期待されます。
まとめ
以上のように、看取り期の対応に関する評価がいくつか見直され、看取り期におけるサービスのさらなる充実が図られております。
Q&A VOL.1
以下にこれまで公表されたQ&Aについてご紹介します。
【訪問介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護】
○ 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)、看取り連携体制加算について①
問 14 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針は、管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、定められていることが必要とされているが、その他に協議を行うことが想定される者としては、医師も含まれるのか。
また、対応方針を定めるにあたっての「協議」とは具体的にはどのようなものか。
(答) 貴見のとおり医師も含まれると考えて差し支えない。また、看取り期における対応方針の「協議」については、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、例えば、通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護支援専門員等の意見を把握し、これに基づき対応方針の策定が行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。
【訪問介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護】
○ 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)、看取り連携体制加算について②
問 15 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。
(答)質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠である。このため、利用者への介護記録等その他の利用者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際に、利用者またはその家族の理解を支援させる目的で、補完的に理解しやすい資料を作成し、これを用いて説明することも差し支えないこととしたものである。
なお、その際、介護記録等の開示又は写しの提供を本人またはその家族が求める場合には、提供することが必要である。
【訪問介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護】
○ 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)、看取り連携体制加算について③
問 16 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。
(答)看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明のことをいう。
○特別管理加算について
問 36 特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。
(答)訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用することはできないため算定できない。ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者のみ特別管理加算の算定を可能とする。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。
↓