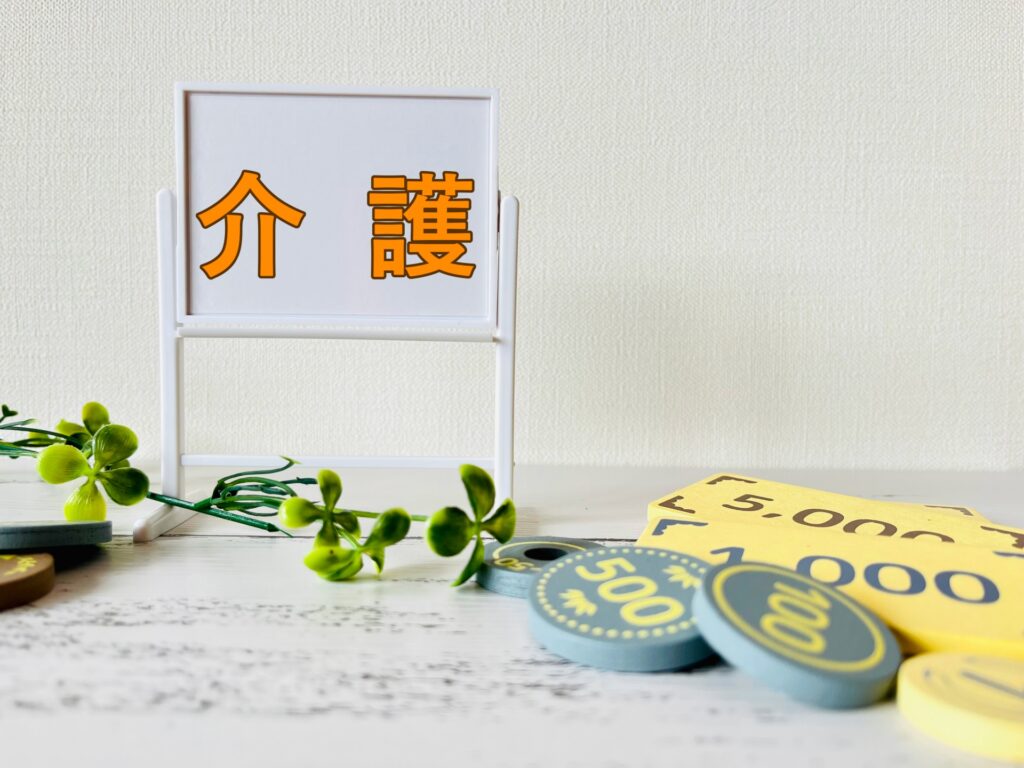
今回は、栄養ケアの推進強化について取り上げます。
高齢者が健康的な生活を送るためには、質の高い栄養管理が欠かせません。
しかし、現在の日本においては、潜在的な低栄養の高齢者が多く存在しており、この問題への対応が急務とされています。
実際、「低栄養の恐れがある」もしくは「低栄養状態」にある高齢者の割合は、要支援者で50%以上、要介護者に至っては70%以上にもなるという報告があります。
さらに、通所サービス事業所を利用している高齢者の40%以上に栄養の問題が見受けられるというデータもあります。
このような状況を踏まえ、R6年度の介護報酬改定では、さらに踏み込んだ対策が求められました。
これまでの取り組み
まずは、令和3年度の報酬改定の取り組みについて見ていきます。
令和3年度の介護報酬改定では、栄養管理に関して以下のような施策が実施されております。
通所・居住系サービスにおける栄養スクリーニングの評価
介護職員による栄養スクリーニングを評価する加算の新設。
施設系サービスにおける栄養管理体制の整備
施設系サービスについて、基本サービスとして栄養管理の体制を整備し、入所者全員への丁寧な栄養ケアを評価する加算の創設。
通所サービスにおける管理栄養士の役割強化
通所サービスについて、管理栄養士が多職種と共同して栄養アセスメントを実施して栄養改善が必要な者を把握し、適切な栄養管理を行うことに対する評評価する加算を創設。
これまでの取り組みで栄養改善に向けた一定の成果が上がってきておりますが、その一方で、以下の課題が指摘されております。
現状と課題
在宅療養者の課題
特に在宅で療養する高齢者に関しては、要介護度が高くなるほど低栄養のリスクが高まり、摂食嚥下機能に問題があるケースも増加しています。
しかし、こうした高齢者に対して訪問栄養食事指導が十分に行われていない可能性があることが指摘されております。
栄養ケアに関する医療機関と介護施設の連携強化
栄養管理や多職種連携を強化するための体制整備は進展しているものの、入院や入所時には、速やかに必要な栄養量や食事形態などを把握して、適切な食事提供や栄養管理につなげる医療機関と介護施設の連携の重要性について意見が出され、「再入所時栄養連携加算」についても、その算定率が導入当初からあまり伸びていないことについて意見があったところです。
在宅での栄養支援の重要性
さらに、退院・退所後の在宅療養における管理栄養士や多職種によるサポートの不足についても指摘がありました。
これら課題について議論がなされ、今回、以下の見直しが行われております。
見直し内容
居宅療養管理指導における管理栄養士の介入強化
対象サービス:居宅療養管理指導
口腔ケアのための歯科衛生士同様、居宅療養管理指導費の算定対象が見直され、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指導について、従来の「通院または通所が困難な利用者」から「通院が困難な利用者」へと対象が拡大されました。
終末期等におけるきめ細かな栄養管理のための算定要件の緩和
対象サービス:居宅療養管理指導
終末期の利用者など栄養管理のニーズが高く、医師が「急性増悪などにより頻回な介入が必要」と判断した場合、特別な指示のもとで管理栄養士が30日間に限り追加訪問を行うことが可能になります。
算定要件(追加内容)
計画的な医学的管理を行っている医師が、急性増悪などで一時的に頻回の栄養管理が必要と判断し、特別な指示を行うことが必要です。
その上で、管理栄養士が利用者を訪問し、栄養管理に関する情報提供や指導・助言を行います。管理栄養士は、30日間に限り、従来の「月2回」を超えて、最大2回の追加訪問が可能となります。
退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
対象サービス:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
退所時における栄養管理の情報連携を強化するため、介護保険施設の管理栄養士が退所者の栄養管理情報を居宅や他の施設、医療機関に提供することを評価する「退所時栄養情報連携加算」が新設されました。この加算は、退所後も栄養ケアが切れ目なく行われるようサポートするものです。
単位数
現行: なし
改定後: 退所時栄養情報連携加算 70単位/回(新設)
算定要件
特別食(腎臓病食や糖尿病食などの疾病治療に基づく食事)を必要とする入所者、もしくは医師が低栄養状態と判断した入所者が対象で、管理栄養士が退所先の医療機関等に栄養管理に関する情報を提供し、1月につき1回を限度として算定される。
再入所時栄養連携加算の対象拡大
対象サービス:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
利用頻度が少ない「再入所時栄養連携加算」についても改定が行われ、対象が拡大されました。これにより、医療機関から再入所する際に特別食などを必要とする利用者が新たに算定対象に加えられ、栄養管理を必要とする利用者に対して切れ目のないサービス提供が強化されます。
算定要件
現行: 二次入所時の栄養管理が一次入所時と大きく異なる者が対象。
改定後: 厚生労働大臣が定める特別食(腎臓病食や糖尿病食などの疾病治療に基づく食事)等を必要とする者が対象。
この改定により、栄養管理が特に重要な高齢者に対して、より柔軟で一貫性のある栄養ケアが提供されることが期待されます。
まとめ
R6年度の介護報酬改定では、栄養ケアについて、居宅療養管理指導や退所時の情報連携が強化されました。
これにより、高齢者に対するより細やかで持続的な栄養ケアが提供される環境が整えられました。
今後も、栄養ケアを通した高齢者のQOLの向上に関する施策が進展していくものと思われます。
以下、これまでに公表されたQ&Aを抜粋してご紹介します。
Q&A VOL.1
問 92 管理栄養士の居宅療養管理指導において、一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示は、同月に2回の指示を出すことはできるか。
(答)
できない。一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示は、その指示の終了する日が属する月に出すことはできない。
問 93 医師が訪問診療を行った同日に管理栄養士による居宅療養管理指導を実施した場合、算定をできるか。
(答)
できる。
↓
