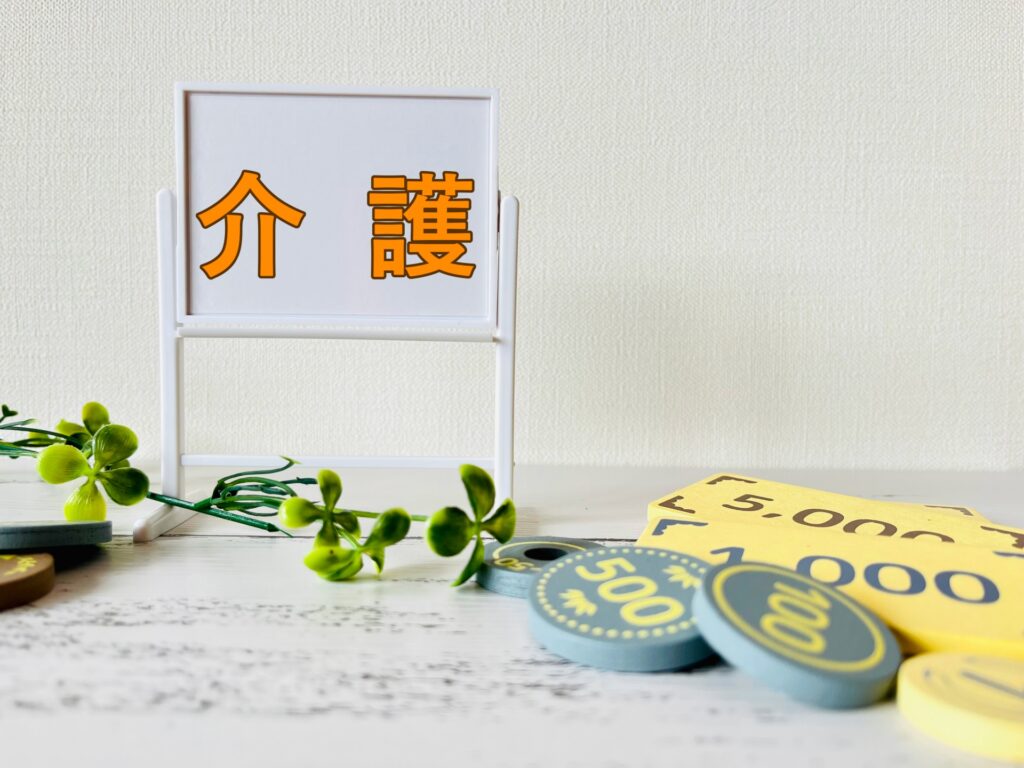
今回は、口腔ケアの推進を取り上げます。
高齢者が健康的な生活を維持するためには、質の高い口腔管理が不可欠とされています。
高齢者は、歯磨きや義歯の適切な管理など、口腔衛生に関する行動を怠りがちで、これにより歯周病などの疾患に罹患しやすくなるだけでなく、食べ物を正しく嚥下できなくなることで、誤嚥性肺炎のリスクも高まるとされています。
このため、令和3年度の介護報酬改定では、施設系サービスにおける「口腔衛生管理体制加算」が廃止され、基本サービスに組み込まれました。また、LIFE対応を要件とする110単位/月の「口腔衛生管理加算(Ⅱ)」が新設されています。
このたび3年間の経過措置を経て、令和6年度より全面的に義務化されることになりました。
その上で、以下の現状を踏まえ、口腔ケアについて、令和6年度もいくつかの見直しが行われました。
現状と課題
1 歯科治療が必要な高齢者の未治療問題
歯科治療が必要な高齢者であっても、治療が行われていないケースが多く、特に在宅療養者ではその割合が高いことが判明しております。
また、訪問サービスや短期入所サービスを利用している高齢者についても、口腔に問題がある利用者を十分に把握できていないという課題が見られました。
歯科医療機関との連携が評価されていないことから、口腔ケアの問題が解決されないまま放置されているケースが多く、介護支援専門員(ケアマネジャー)による歯科医師への情報提供も約3割にとどまっています。
情報提供が行われなかった理由としては、「伝えるべき情報を取得していない」という点が報告されています。
2 特定施設における口腔アセスメントの不足
特定施設において、利用者の57.8%が歯科治療を必要としているにもかかわらず、定期的な口腔アセスメントを受けていたのはわずか26.2%にとどまっていることが判明しております。
さらに、大部分の利用者について、個々の口腔の状態が十分に確認されておらず、口腔衛生管理に関する取り組みが必要であるとされております。
3 終末期がん患者の口腔ケアの頻度増加
終末期がん患者については、全身状態が低下するにつれて口腔衛生管理の頻度が増加するという報告があります。
また、診療報酬の看取り加算が算定された患者について、看取り加算が算定された日から1か月以内に歯科診療を受けた日数が月4日を超えるケースも一定数確認されたところです。
4 介護保険施設におけるスクリーニングの未実施
介護保険施設の入所者の中には、歯科専門職の介入が必要でありながら、介入が行われていないケースが報告されております。
また、入所者全員に対する口腔スクリーニングを実施していない施設は、介護老人保健施設で46.1%、介護医療院では41.8%に上ることが明らかとされました。
加えて、口腔スクリーニングを実施していない理由として、「スクリーニングの指標がない」といった要因が挙げられており、この点についての対応不足が課題として指摘がありました。
上記の現状と課題を踏まえて、今回、以下の見直しが行われました。
改定の内容
1 居宅療養管理指導における歯科衛生士の介入強化【居宅療養管理指導★】
居宅療養管理指導費の算定対象が見直され、これまで「通院または通所が困難な方」に対して月4回までの居宅療養管理指導費の算定が可能でしたが、改定後は「通院が困難な方」であれば対象となることになりました。
これにより、通所サービスを利用している方でも、通院が困難な場合は歯科衛生士等の指導がより受けやすくなり、口腔ケアのサポートがさらに強化されることが期待されています。
2 訪問系・短期入所系サービスにおける口腔管理の連携強化【訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
介護職員などが利用者の口腔の健康状態の評価を行い、その結果を利用者の同意のもとで歯科医療機関や介護支援専門員に情報提供することが評価される新しい加算「口腔連携強化加算」が設けられました。
この加算は、月に1回のみ算定可能で、1回あたり50単位が加算されます。
事業所がこの加算を受けるためには、口腔の健康状態の評価を行い、利用者の同意を得て、歯科医療機関やケアマネジャーに評価結果を提供する必要があります。
また、事業所は歯科医師や歯科衛生士との連携体制を整備し、従業者が適切に相談できる体制を確保することが求められています。
3 がん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実【居宅療養管理指導★】
終末期のがん患者に対する口腔ケアの重要性が高まる中、今回の改定で、終末期がん患者について、居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合)の算定回数の上限が緩和されました。
がん末期の利用者に対して、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が訪問して実地指導を行った場合、1か月に最大6回まで算定できるようになりました(通常は4回が上限)。
4 特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化【特定施設入居者生活介護★】
全ての特定施設入居者生活介護において、これまで算定されていた「口腔衛生管理体制加算(30単位/月)」は廃止され、口腔衛生管理を基本サービスとして行うことが省令により義務化されました。
この改定により、施設全体での口腔衛生管理体制が標準化され、すべての入居者が適切なケアを受けられるようになります。
また、この新しい取り組みが円滑に進むよう、3年間の経過措置期間が設けられました。
この間に施設側は、口腔衛生管理体制の整備を進め、入居者が自立した日常生活を送るために必要な口腔ケアを計画的に提供することが求められることになりました。
5 介護保険施設における口腔衛生管理の強化【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
介護保険施設が歯科専門職と連携して、利用者の入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能について評価することが義務付けられました。
これにより、施設側は入所時に加え、月に1回程度、従業者または歯科医師や歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が入所者ごとの口腔健康状態を確認することになります。
なお、歯科医師や歯科衛生士は、施設との連携体制について文書で取り決めを行い、実施事項を明確にすることが求められています。
まとめ
今回の見直しにより、令和6年から義務化される介護施設での口腔衛生管理と相まって、在宅サービス従業員と施設サービス従業員の双方において、高齢者の口腔ケアに対する意識が一層高まることと思われます。
これにより、高齢者の健康維持と向上が長期的に促進されることが見込まれます。口腔衛生が健康の基礎的要素であるという認識が、介護職員の間に広く浸透し、質の高いケアを支える基盤となっていくことが期待されます。
以下、これまでに公表されたQ&Aについて抜粋してご紹介します。
Q&A VOL.1
問 179 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。
(答)入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定できる。
問 180 口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
(答)施設ごとに計画を作成することとなる。
Q&A VOL.6
口腔機能向上加算について
問1 平成 21 年介護報酬改定に関する Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)問1において、「口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。」という問があるが、令和6年度介護報酬改定において、医療保険における歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法との算定についての記載が削除されたが、当該事務連絡についての取扱はどうか。
(答)
平成 21 年介護報酬改定に関する Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)問1は、令和6年度介護報酬改定をもって廃止されたい。
なお、留意事項通知の通り介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、口腔機能向上加算を算定できないことには留意されたい。
(参考)
※ 平成 21 年介護報酬改定に関する Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)問1
問1 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。
(答)
歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。
↓
