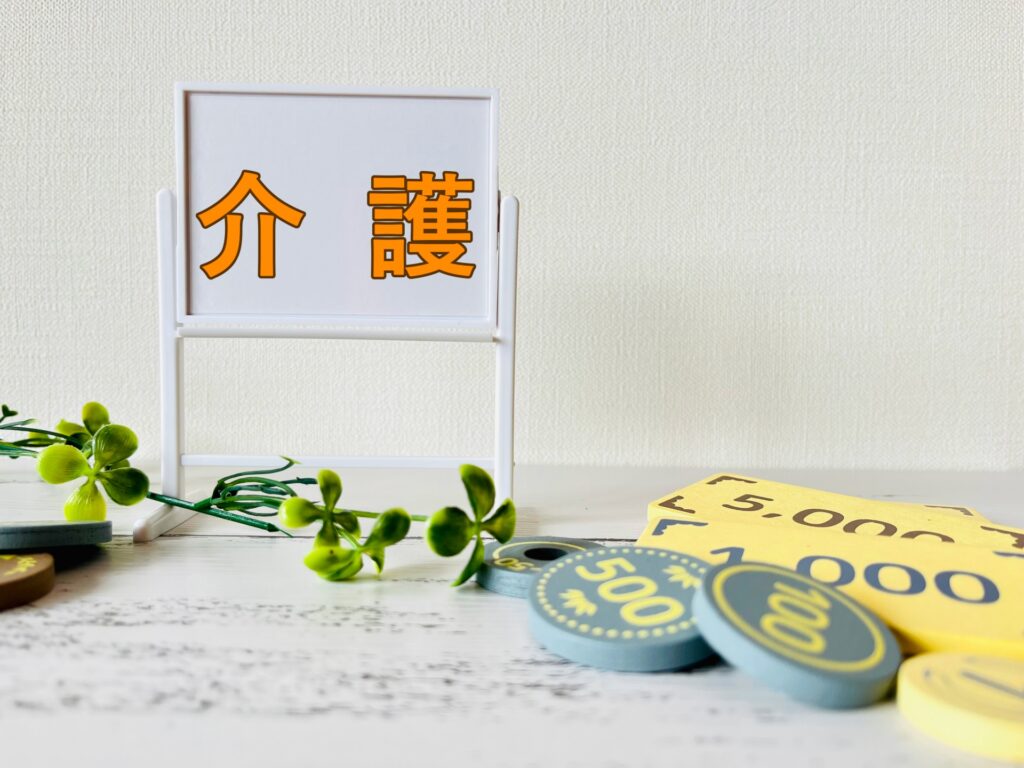
2024年度(R6年度)の介護報酬改定が、3年ぶりに実施されました。今回の改定は、介護を必要とする高齢者やその家族にとって、とても重要な変化をもたらします。
特に、認知症や単身高齢者、中重度の高齢者が安心して地域で生活できるよう、医療機関との連携強化や新しい支援策が盛り込まれています。
見直しの背景と課題
その背景としては、
・2025年には団塊世代が75歳以上となり、高齢者人口が増加。さらに2040年頃には85歳以上の人口が増加し、生産年齢人口が減少する中で、介護人材の確保や経営環境の整備が重要な課題となっていること、
・2040年に向け、認知症患者や単身高齢者の増加が懸念されており、地域ごとに異なる状況に対応するため、地域包括ケアシステムの深化と推進が必要であること、また、医療と介護の連携や感染症対応の強化が求められていること、
・介護職員の確保が難しい状況で、賃上げやテクノロジーの導入により介護職の働きやすさを改善し、人材の確保と質の高いサービス提供が課題であること、
・介護制度の安定性と持続可能性を高めるため、給付と負担のバランスを調整し、効率的で持続可能な制度運営が求められていること、
などがあげられます。
これら背景と課題に鑑み、報酬改定により以下の取り組みが期待されております。
医療機関との連携強化で、地域医療をもっと身近に
今回の改定では、在宅での医療ニーズにしっかりと対応するため、医療機関との連携がさらに強化されます。特に認知症や重度の高齢者にとって、日常のケアと医療がより密接に連携することで、安心して暮らせる環境が整えられるのは大きな前進です。
たとえば、在宅医療や訪問診療を受ける高齢者が増えている昨今、医療と介護の境界を超えた支援が求められています。今回の改定は、そのニーズに応えるため、地域全体で高齢者を支える体制をさらに強化していきます。
リハビリ、口腔ケア、栄養管理の一体化を推進
高齢者の自立を支援するため、リハビリテーションや栄養管理の重要性もますます高まっています。今回の改定では、リハビリ、口腔ケア、栄養管理を一体的に提供することで、高齢者が健康で自立した生活を送れるような仕組みが強化されます。
さらに、サービス事業者と歯科医療機関が連携し、口腔ケアや栄養管理を統合的に進める取り組みが進行中です。「健康な口から健康な生活へ」を合言葉に、日々の食事やリハビリがしっかりサポートされる環境が整備されていくものと思われます。
介護職員の処遇改善とサービスの質向上
介護の現場を支える介護職員の待遇改善も、今回の改定で注目されるポイントです。介護人材の確保が年々課題となっている中、介護職員の処遇改善はもちろん、データ活用による生産性向上にも取り組みます。これにより、介護サービスの質がさらに向上し、利用者にとってもより良いサービスが期待できるようになります。
訪問介護の報酬体系と夜間対応の見直し
報酬体系の適正化も今回の改定の一環です。訪問介護における「同一建物減算」についてはさらに見直され、報酬が整理されることになりました。
また、夜間対応型訪問介護については、利用者の負担に配慮した新たな区分が設けられます。夜間の見守りやケアが必要な高齢者にとって、これによりさらに安心して暮らせる環境が整うものと思われます。
情報公開の義務化で、事業所選びがもっと透明に
事業所の運営について、これまでは「書面掲示」のみが義務づけられていましたが、今回の改定でインターネット上での情報公開が義務化されます。
これにより、事業所の運営内容や重要事項をウェブサイトで確認できるようになり、利用者やその家族がサービス選びをする際の参考にしやすくなります。
通所サービスの送迎も柔軟に
通所系サービスの送迎についても新たな運用が導入されました。これまでは利用者の居住実態のある場所への送迎が中心でしたが、今回の改定では、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者と同乗することが可能になります。
これにより、送迎の効率が上がり、利用者にとってもサービスの利便性が高まります。
まとめ
R6年度の介護報酬改定は、地域で安心して暮らせるように、医療機関との連携強化や自立支援の強化を中心にさまざまな新しい取り組みが導入されました。
介護職員の処遇改善やデータ活用による生産性向上など、介護の質を高めるための工夫も見られます。これからの介護サービスの進化に期待が高まります。
介護が必要な家族や自身の将来に向けて、こうした制度改定をしっかり理解しておくことで、より良い選択につながっていくものと思われます。
↓
