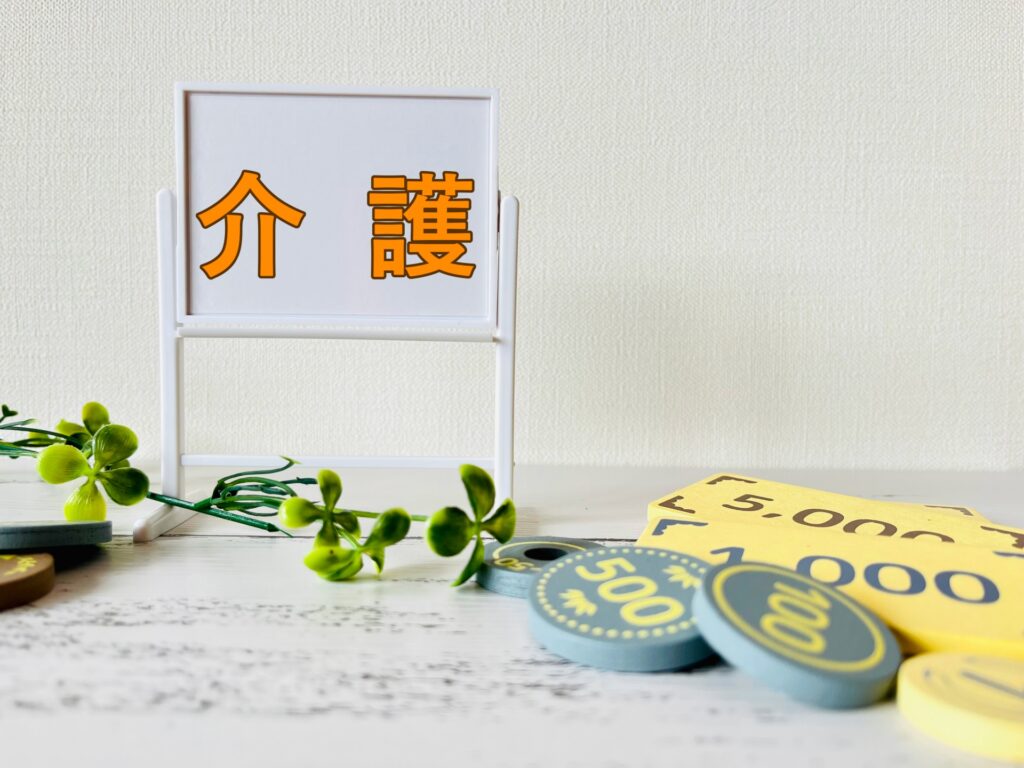特定事業所加算とは専門性の高い人材の確保やサービスの質の向上に取り組む事業所を評価する制度です。
算定要件に合致することを事前に指定権者(都道府県・市区町村)に届け出る必要があります。
介護保険法における適用サービスは訪問介護サービスと居宅介護支援サービスのみとなっております。
今回の報酬改定は、看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から行われており、改定のポイントは以下のとおりです。
訪問介護 特定事業所加算 改定のポイント
○看取り期の利用者など重度者へのサービス提供を行っている事業者を評価する要件を追加
○従来の加算Ⅳを廃止し、Ⅴを加算Ⅳに変更
○中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を評価(加算Ⅴ)
○重度要介護者等への対応における現行要件について見直し(加算Ⅰ、Ⅲ)
看取り期にある利用者については、ケアマネへの報告や医療機関との連携が多くなるといったことが評価されて、算定要件に加えられました。
利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の60以上の場合に加算されていた旧加算Ⅳは利用が少なかったことから、廃止されました。
また、加算Ⅰ~Ⅳ各区分同士を併せて算定することはできませんが、中山間地域等の事業者を対象とした加算Ⅴとそれぞれの加算(Ⅰ~Ⅳ)を併せて算定することは可能となっております。
加算Ⅲについては、これまで人材要件を含まれていなかったのですが、新たに人材要件が加わりました。
以下、新たに加わった要件とその対象となる加算を紹介します。
訪問介護 特定事業所加算 新たな算定要件
(6)病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等【加算Ⅰ・Ⅲ】
(7)通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること(加算Ⅴ)
(8)利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること(加算Ⅴ)
(11)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること 【加算Ⅲ・Ⅳに追加】
(12)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること⇒【加算Ⅲに追加】
(12)利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の60以上 ⇒【削除】
(14)看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)
※(6)病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等
▶加算(Ⅰ)・(Ⅲ)については、 (13)または(14)を満たす場合に算定できることとする。また、(14)を選択する場合には(6)を併せて満たす必要があるとされました。
※(13)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の20以上
<R6年度Q&A>今回の訪問介護の特定事業所加算の改正についてQ&Aを見てみます。
Q&A VOL.1
○ 特定事業所加算について①利用実績と算定期間の関係性
問1 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前 12 月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。
(答)
算定要件に該当する者の対応実績と算定の可否については以下のとおり。
| 前年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 対応実績 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 算定可否 | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 当該年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 対応実績 | ||||||||||||
| 算定可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✖ |
○看取り期の利用者への対応体制について
問2 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師との連携により 24 時間連絡できる体制を確保することとされているが、具体的にどのような体制が想定されるか。
(答)
「24 時間連絡ができる体制」とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することを要するものではなく、夜間においても訪問介護事業所から連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要な場合には事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。
具体的には、
イ 管理者を中心として、連携先の訪問看護ステーション等と夜間における連絡・対応体制に関する取り決め(緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法等を含む)がなされていること。
ロ 管理者を中心として、訪問介護員等による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば連携先の訪問看護ステーション等に連絡するか)がなされていること。
ハ 事業所内研修等を通じ、訪問介護員等に対して、イ及びロの内容が周知されていること。
といった体制を整備することを想定している。
←訪問介護員が常に事業所にいる必要はなく、緊急時には出勤できる体制が整っていれば問題ないようです。連携体制の具体例としては、夜間の連絡体制を訪問看護ステーションと取り決めておき、観察項目を標準化して、異常があれば迅速に対応できる仕組みを整備し、職員への研修でこれらの内容を周知するなどが必要のようです(ブログ主)
○ 特定事業所加算について③中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制の算出方法
問3 特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。
(答)
中山間地域等に居住する者への対応実績については、利用実人員を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、前3月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。
| 居住地 | 特別地域加算等※の算定状況 | 利用実績 | |||||
| 中山間地域等 | それ以外の地域 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 1 | 利用者A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 利用者B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 利用者C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 利用者D | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 利用者E | ○ | ○ | ○ | |||
(※)特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含めない。
(注2)特別地域加算等の算定を行っている利用者に関しては計算には含めない。
・中山間地域等に居住する利用者(A,D(特別地域加算等を算定する利用者 C を除く))
2人(1月)+2人(2月)+1人(3月) =5人
したがって、対応実績の平均は5人÷3月≒1.6 人≧1人
なお、当該実績については、特定の月の実績が1人を下回ったとしても、前年度又は前3月の平均が1人以上であれば、要件を満たす。
←中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供実績が求められますが、この実績は前3ヶ月の平均値をもとに計算されます。具体例として、1月~3月の利用者数をもとに算出されたものが紹介されております(ブログ主)。
○ 特定事業所加算について④月の途中で居住地が変わった場合
問4 特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
(答)
該当地域に居住する期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
←該当地域に住んでいた期間のみ加算対象となるので注意が必要です。(ブログ主)
○ 特定事業所加算について⑤個別サービス計画の見直しに関わる職種等
問5 新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、「利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行うこと」とされているが、訪問介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、訪問介護計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
(答)
・ 特定事業所加算(Ⅴ)を算定する訪問介護事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援することが求められている。当該加算を算定する事業所においては、中山間地域等にあって、必ずしも地域資源等が十分ではない場合もあることから、訪問介護事業所のサービス提供責任者が起点となり、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、継続的なサービス提供を行うことと併せて、他の地域の訪問介護事業所とは異なる「特有のコスト」を有しているため、特定事業所加算により評価するものである。
・ 訪問介護事業所における訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。
・ また、訪問介護計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき訪問介護計画の見直しが行われていれば,本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり、書類を作成することは要しない。
←全ての職種が毎回関与する必要はなく、必要に応じた職種が関われば十分なようです。また、会議を新たに設ける必要もなく、日常業務の中での連携を通じて計画を見直すことも可能なようです。
○ 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)
問6 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を 30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。
(答)
勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の一定の資格を有する訪問介護員等の割合を要件)と同様に、前年度(3月を除く 11 ヶ月間。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。
←勤続年数が7年以上の訪問介護員等を 30%以上とする要件における具体的な割合は、前年度または届出日の前3ヶ月間の実績を基に計算されます。
○ 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)
問7 「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が 30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
(答)
・ 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)における、勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合に係る要件については、
- 訪問介護員等として従事する者であって、同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合を要件としたものであり、
- 訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないこと(例えば、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等として従事する前に、同一法人等の異なるサービスの施設・事業所の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算して差し支えないものである。)。
・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、
- 同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数
- 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。
(※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。
○ 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)
問8 勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
(答)
産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
Q&A VOL.6
○ 特定事業所加算
問1 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前年度又は算定日が属する月の前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。
(答)
算定要件に該当する者の対応実績と算定の可否については以下のとおり。(前々年度には対応実績がなかったものとした場合)
| 前年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 対応実績 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 算定可否 | ✖ | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 当該年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 対応実績 | ||||||||||||
| 算定可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問介護に関わる特定事業所加算の改正において、以上のポイントをしっかり理解し、事業運営に活かしていきましょう。
↓