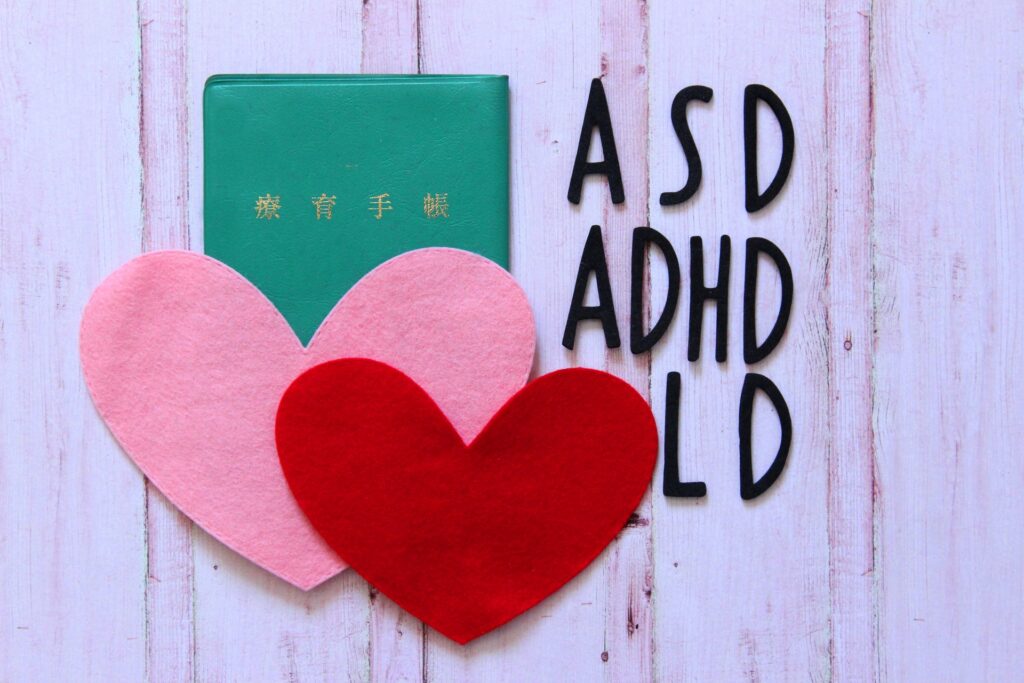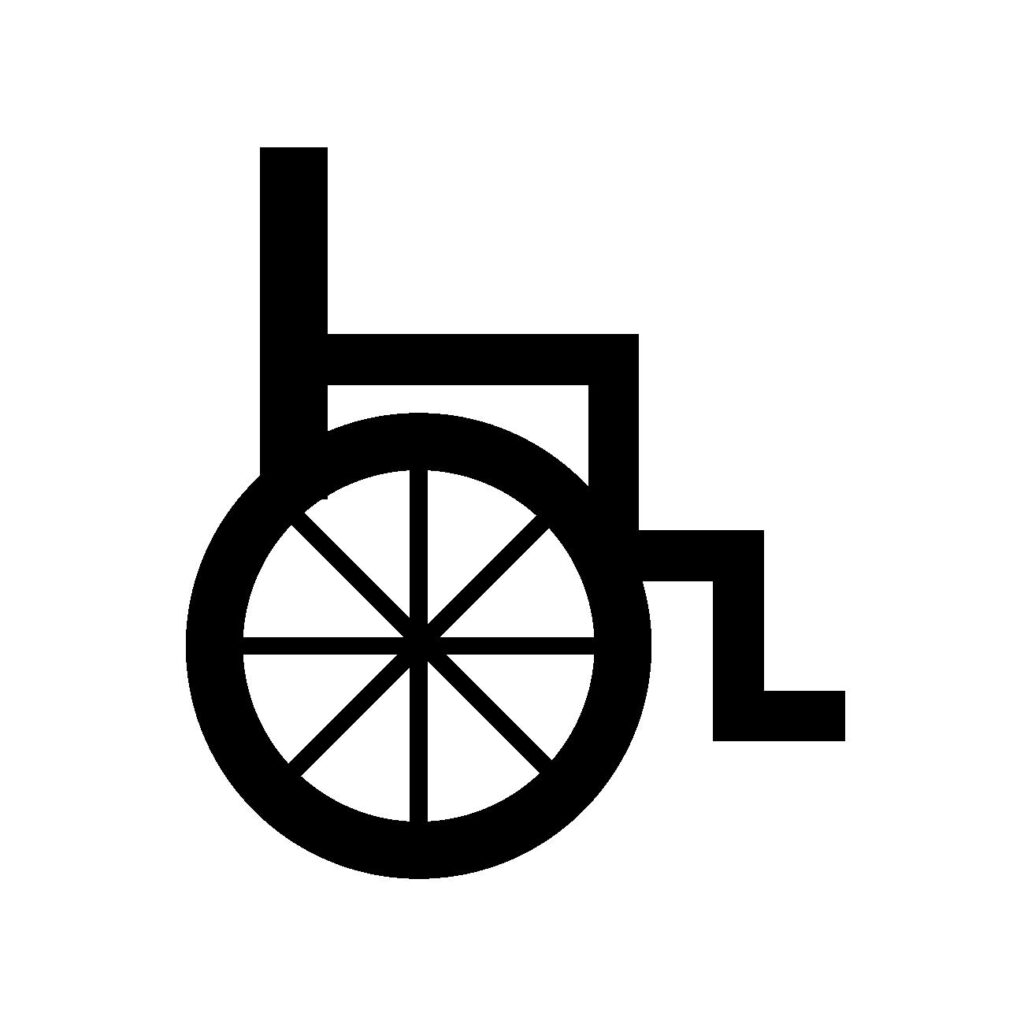令和6年度の障害福祉サービス報酬改定では、グループホームにおける支援の質を高めるための取り組みも注目されています。
今回、その背景や具体的な改定内容についてご紹介します。
グループホームの現状と問題意識
近年、グループホームには営利企業の参入が増えています。これに伴い、障害福祉サービスの経験や実績が十分でない事業者も増えてきたため、利用者の障害特性や障害程度に応じた適切な支援が提供されていないという懸念が指摘されています。
また、グループホームは生活の場でありながら、閉鎖的な運営になりやすいという問題もあります。そのため、地域社会との連携を強化し、事業運営の透明性を確保する必要があるとの声がありました。
改善への提案
こうした問題を解決するため、介護分野で導入されている「運営推進会議」の仕組みを参考とした、外部の関係者を定期的に取り入れる仕組みが提案されました。
※介護保険運営推進会議の概要
<目的>
各地域密着型サービス事業者が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにして、事業者による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として、自ら設置するもの。
<構成員>
・利用者
・利用者の家族
・地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等)
・市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、有識者
<開催頻度>
2月に1回以上~6か月に1回程度
<会議の内容>
事業者は、サービスの提供状況等を報告し、会議による評価を受け、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける
<記録の作成と公表>
報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し、記録を公表(事業者の義務)
今回の改定内容
運営基準が改正され、令和6年度は地域連携推進会議を開設することが努力義務となりました。令和7年度から義務化されます。地域連携推進会議の内容は以下の通りです。
・地域連携推進会議の開催
利用者やその家族、地域住民の代表者、市町村の担当者などが参加する「地域連携推進会議」を少なくとも年に1回開催し、グループホームの運営状況を報告する場が設けられます。また、必要な要望や助言を聴く機会も提供されます。
・施設見学の機会の提供
会議の構成員に対して、少なくとも年に1回、施設を見学する機会を提供することが義務化されました。
・記録の公表
会議の内容や要望、助言についての記録を作成し、公表することが求められます。
まとめ
今回の改定により、グループホームの支援の質を高めるための取り組みがより具体的になりました。地域社会との連携を強化し、外部の目を取り入れることで、より透明性を持った運営が進められることが期待されます。
以下、これまでに公表されたQ&Aを抜粋してご紹介します。
Q&A VOL.1
問 48 地域連携会議の構成員として「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等」と示されているが、例示された全ての者が参画する必要があるのか。また、当該会議には全ての構成員の出席が必須か。
(答)
利用者、利用者家族、地域住民の代表者は必ず参画することが望ましい。また、市町村担当者等については、当該市町村に多数の施設等がある場合等、出席が難しい場合もあるため、可能な範囲での出席が望まれる。
(地域連携推進会議②)
問 49 「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。
(答)
事業所の所在市町村となる。
Q&A VOL.3
問 12 「地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。」とされており、これらについて記録を作成・公表するものと示されているが、公表の方法はどういうものが想定されるか。
(答)
ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの者が閲覧可能となるよう広く公表することが望ましい。
↓