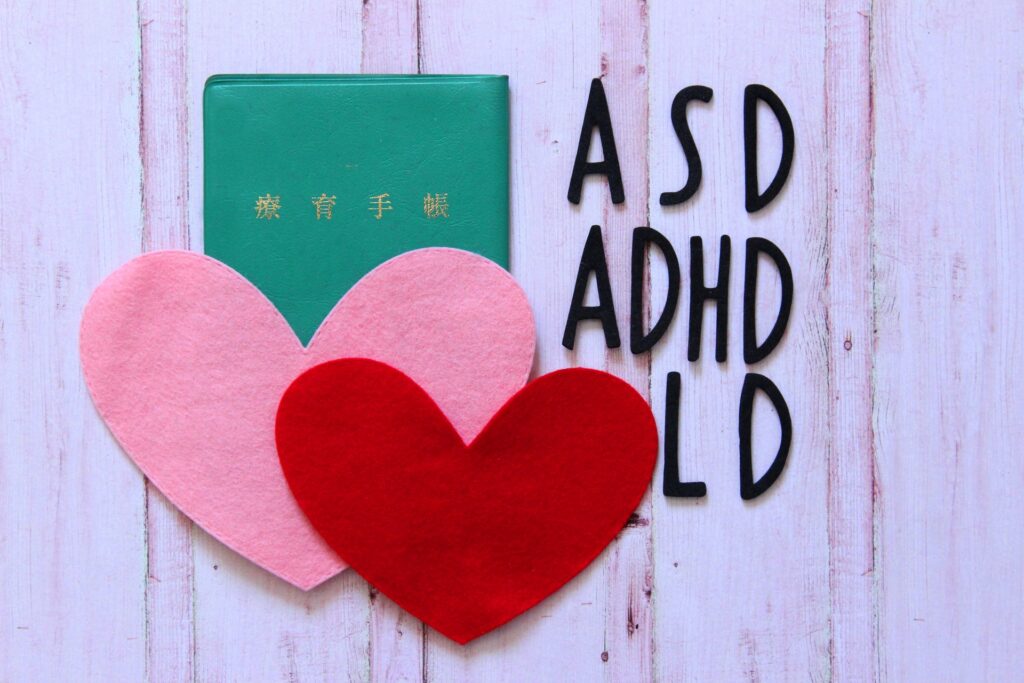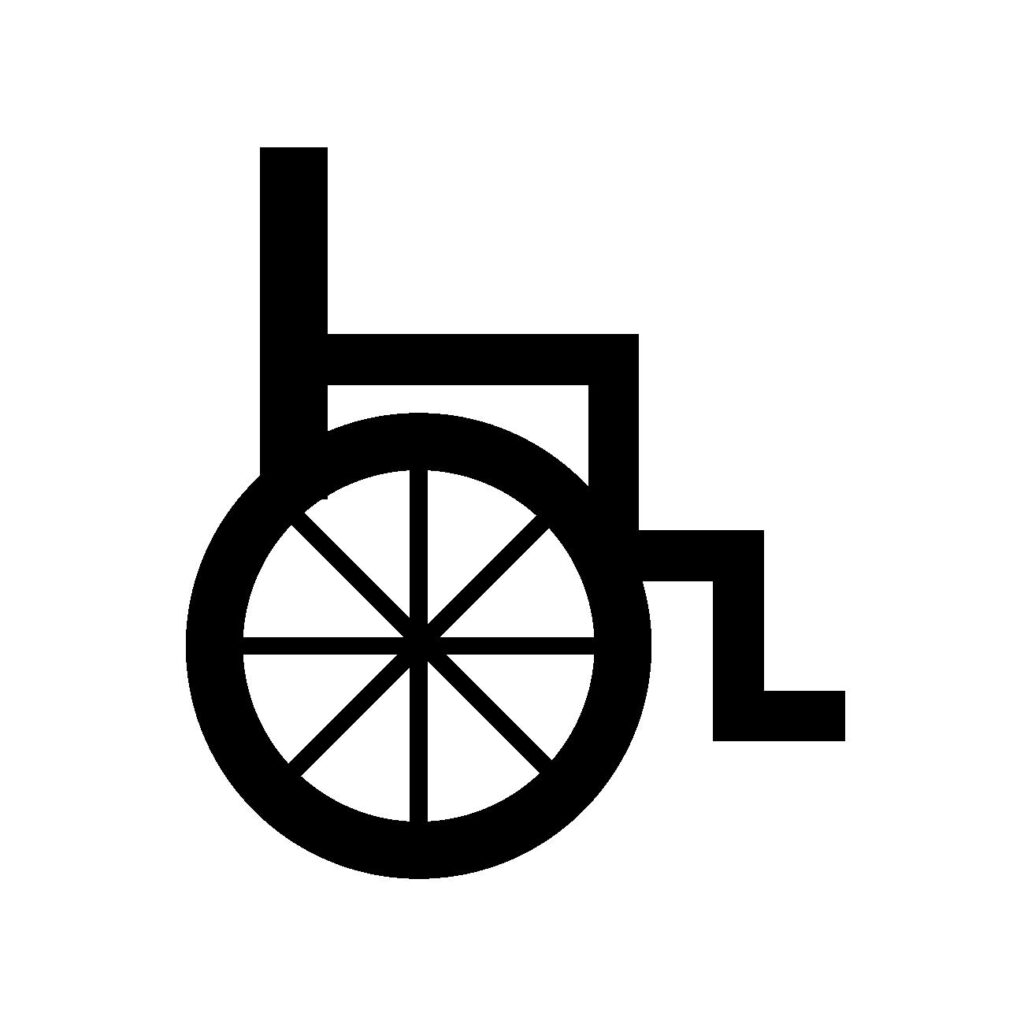
生活介護の報酬改定2回目です。今回はリハビリテーションの配置基準、栄養ケア・マネジメントの強化、食事提供体制加算についてです。
リハビリテーション職の配置基準の見直し
生活介護の人員配置基準においては、理学療法士又は作業療法士を配置することとされておりますが、その確保が困難な場合には、看護師や言語聴覚士等を機能訓練指導員として配置することができると規定されております。一方、介護保険制度における通所介護においては、理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合に関わらず、言語聴覚士を配置することができることになっているところです。
現在、生活介護の利用者の中には、交通事故などの高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する方もいて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練が必要な場合もあります。そのため現場の実態に合わせ、リハビリテーション職の配置基準が見直されました。
≪リハビリテーション配置基準≫
<現行>
指定生活介護事業所には以下の職員を配置する。
・看護職員、理学療法士または作業療法士、生活支援員
↓
<見直し後>
指定生活介護事業所には以下の職員を配置する。
・看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員
リハビリテーション加算におけるリハビリテーション実施計画の作成期間の見直し
リハビリテーション加算の条件として、「リハビリテーション実施計画」を概ね3か月ごとに作成することが求められていましたが、今回の改定で個別支援計画の作成期間に合わせ、6か月ごとに作成することになりました。この変更により、関係者の負担軽減が見込まれます。
≪リハビリテーション実施計画の作成期間≫
<現行>
リハビリテーション実施計画原案に基づき、概ね2週間以内および3か月ごとに評価とアセスメントを行い、その後、リハビリテーションカンファレンスを実施して計画を作成。
↓
<見直し後>:
リハビリテーション実施計画原案に基づき、概ね2週間以内および6か月ごとに評価を行い、その後、計画を作成。
今回の改定は、リハビリテーション職の確保が難しい現状を踏まえ、利用者のニーズに応じた柔軟な対応を可能にするための見直しとなっております。
栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実
生活介護の現場では、生活習慣病を有する者の割合が高く、早食い、丸呑みが見られたところです。
そのため、BMI等の測定による健康管理を継続的に行い、その結果を踏まえて食事提供への配慮を行うこととし、栄養等に課題を抱える重度の障害者に対して、栄養状態のスクリーニングを実施しリスクのある者に対しては、個別に栄養管理を行う等の栄養ケア・マネジメントを行うよう見直されました。
介護保険同様、生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価が新設されました。
≪栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取り組み≫
栄養スクリーニング加算【新設】 5単位/回
利用者の利用開始時および利用中の6か月ごとに栄養状態を確認し、その結果を相談支援専門員に提供した場合に加算されます。
栄養改善加算【新設】 200単位/回
低栄養または過栄養にあるなどの利用者に対し、個別的に栄養改善サービスを提供した場合に加算されます。3か月ごとの栄養状態の評価を行った場合、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として所定単位数を加算されます。必要があれば引き続き栄養改善サービスを提供できます。
栄養改善加算の条件
栄養改善サービスの加算を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
・管理栄養士の配置
事業所内に1名以上の管理栄養士を配置、または外部連携により確保すること。
・栄養ケア計画の策定
利用開始時に栄養状態を把握し、管理栄養士と共同で、利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態に配慮した栄養ケア計画を策定。
・個別の栄養管理の実施
栄養ケア計画に基づき、必要に応じて管理栄養士が利用者宅を訪問し、栄養改善サービスを提供し、定期的に栄養状態を記録。
・栄養ケア計画の評価
定期的に栄養ケア計画の進捗状況を評価し、適切な栄養管理を継続。
今回の改定により、生活介護利用者の栄養状態に対するきめ細やかな管理が求められ、栄養ケアが一層強化されます。利用者の健康維持や生活の質向上を目指した重要な取り組みとなります。
食事提供体制加算の見直しと経過措置の延長
これまで、食事提供体制加算に関しては、障害児者の特性に応じた配慮や、食育的な観点を含めた検討が進められてきました。また、他の制度とのバランスや、在宅で生活する障害者との公平性といった点も考慮されてきました。
今回の報酬改定では、特に栄養面での配慮が評価されるようになり、管理栄養士や栄養士が献立作成に関与することや、摂食量・BMIなどの定期的な記録や評価が求められています。一方で、他制度とのバランスや公平性を保つために、経過措置が継続されることも決定しました。
≪食事提供体制加算の見直し≫
<現行>
収入が一定額以下の利用者に対して、原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する
↓
<見直し後>
現行の要件に加え、
・管理栄養士や栄養士の関与
食事提供において、管理栄養士や栄養士が献立作成に関わる、または献立の確認を行うこと。
・摂食量の記録
利用者ごとの摂食量を記録し、食事の提供と健康状態の関連を把握する。
・BMI等による定期的な評価
利用者ごとの体重やBMIを定期的に記録し、栄養状態の変化を追跡する。
経過措置の延長
これらの変更に伴い、現在の食事提供体制加算に関する経過措置が令和9年3月31日まで延長されることになりました。
以下、これまで公表されたQ&Aを抜粋してご紹介します。
Q&A VOL.5
(食事提供体制加算)
問1 食事提供体制加算の算定要件として、法人内に管理栄養士等を配置していない場合は、公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等の管理栄養士等が献立の作成や確認を行うこととされているが、献立に関して具体的に何を確認してもらう必要があるのか。
(答)
食事の献立は、利用者の心身の状況(性・年齢、身長・体重、疾病など)、嗜好を考慮するとともに、障害の特性に応じた適切な栄養量の設定及びそれを踏まえた内容の献立(調理の方法含む)である必要がある。
献立の内容確認については、例えば、栄養ケア・ステーション等が、各事業所において設定する給与栄養目標量※を踏まえた献立になっているかどうかを確認するといった方法がある。なお、各事業所において、栄養士を配置していないなどにより給与栄養目標量の設定が困難な場合は、栄養ケア・ステーション等に対し、作成した献立の提供と併せて、給与栄養目標量を設定するために必要な利用者の心身の状況の情報提供を行うことで、栄養ケア・ステーション等はその内容を基に給与栄養目標量の設定と、その内容を踏まえた献立について適切な助言を行うことになる。
また、献立の確認の範囲については、提供する食事の全ての献立を確認することは困難であることから、各事業所において設定している一定期間の献立(サイクルメニュー)を確認してもらうことで足りる。なお、サイクルメニューは、各事業所において定める期間が異なることから、各々の施設の状況を踏まえて対応すること。
↓