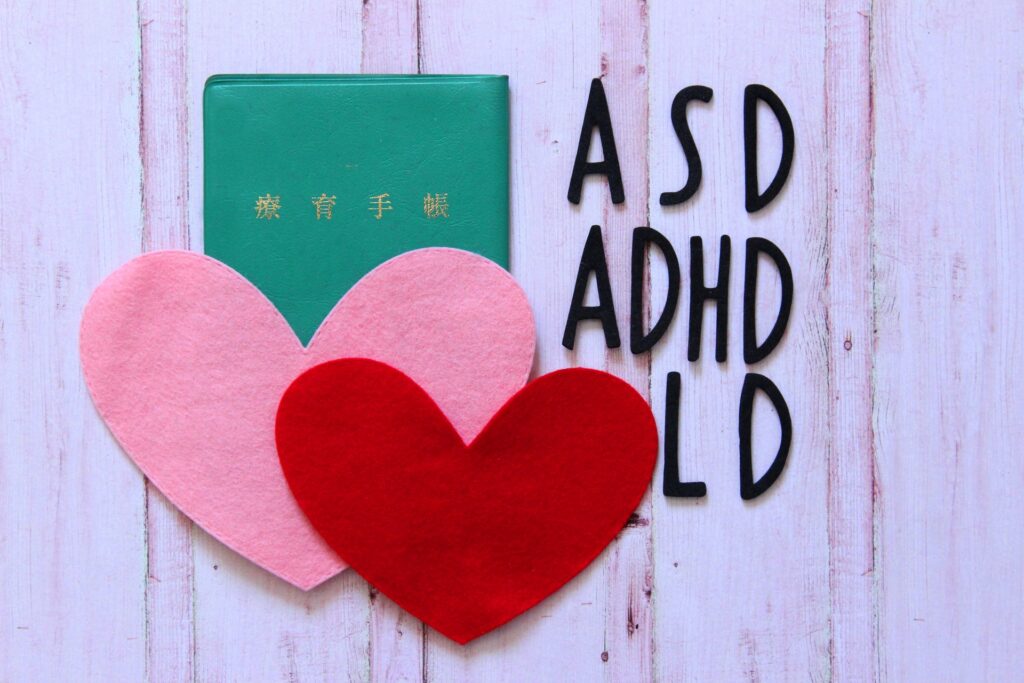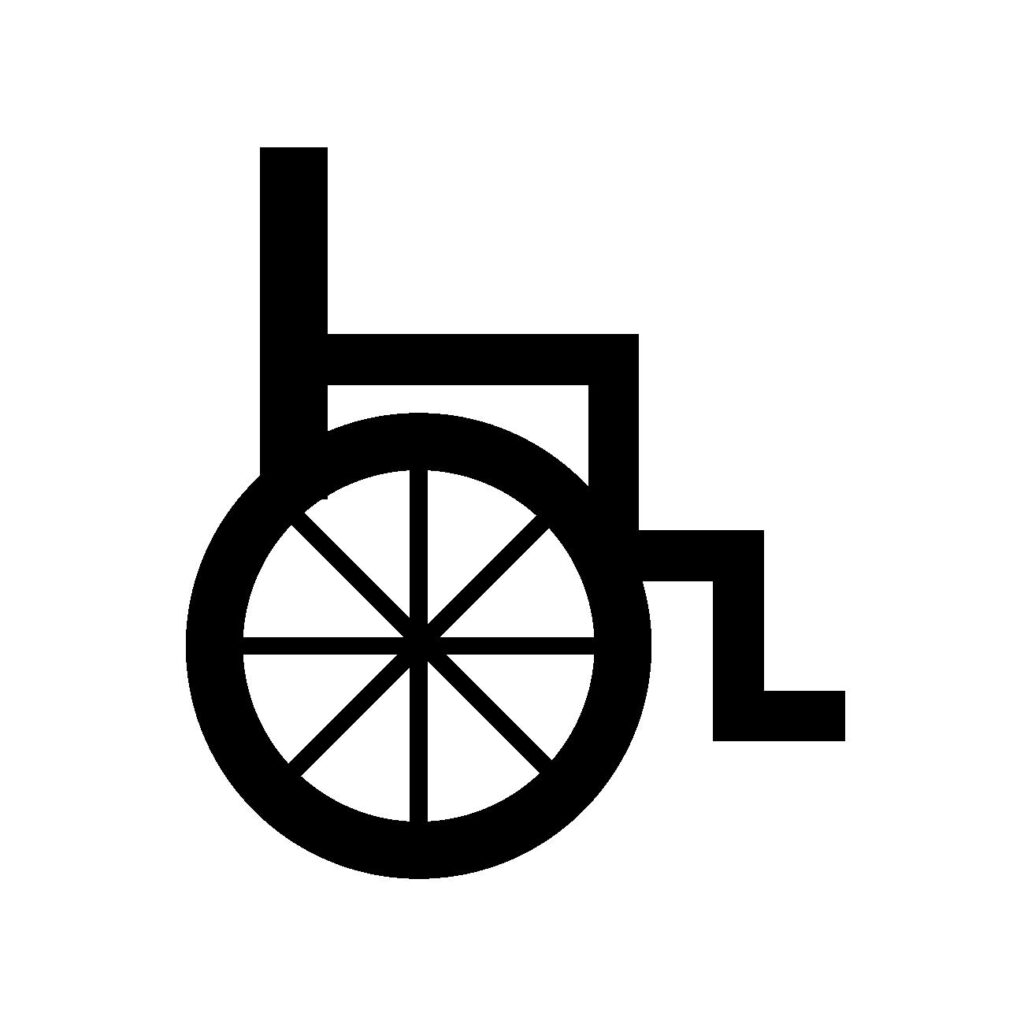
2024年の障害福祉サービス報酬改定では、強度行動障害を持つ障害者や児童が地域で安心して生活できるための支援体制が大幅に強化されました。特に、支援が必要な人々がどの地域でも適切な評価を受け、質の高いサポートが提供されるよう、多くの改定が行われています。
今回はその中でも、「重度障害者支援加算」と「集中的支援加算」について詳しく見ていきましょう。
強度行動障害を有する障害児者の受け入れ体制強化
強度行動障害を持つ児者(児童・障害者)の支援体制が強化されます。特に、支援が難しいとされる高い行動関連項目を持つ方々の受け入れが拡大され、適切なサポートを行った事業所が評価されることになりました。加えて、事業所には「中核的人材」と呼ばれる、強度行動障害を持つ方々へのチーム支援を管理する専門的なスタッフの配置が求められ、その配置も評価の対象となります。
【生活介護・施設入所支援における重度障害者支援加算】
区分6以上、行動関連項目が10点以上の報酬区分が新設されました。
「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)」修了者の加配要件を廃止し、生活支援員のうち基礎研修修了者が20%以上で評価されるように見直されました。
【短期入所における重度障害者支援加算】
区分4および5の新しい報酬区分を設け、強度行動障害支援者養成研修修了者による支援計画が作成された場合に評価が新設されました。
【共同生活援助における重度障害者支援加算】
利用者の状態や環境の変化に対応する初期のアセスメント評価が新たに設けられました。
【重度障害者支援加算(共通)】
さらに、全サービス(生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助)で、行動関連項目が18点以上の者に対して中核的人材が作成する支援計画を実施した場合、加算がさらに適用されます。
状態が悪化した強度行動障害者への集中的支援
状態が悪化した強度行動障害者への「集中的支援」が新たに評価対象となります。広域的な支援を行う専門家が、事業所や施設を集中的に訪問し、環境調整やアセスメントを行う取り組みが評価される仕組みです。この集中的支援は、最長3か月の期間で提供されます。
【集中的支援加算】
専門的な支援人材が訪問などを行った場合に1回あたり1,000単位(月4回まで)。
状態が悪化した方を受け入れた施設等に対しては、1日あたり500単位の評価。
行動援護における短時間の支援評価
強度行動障害を有する人に対する支援の質を高めるため、行動援護の報酬設定も見直されました。特に、短時間の支援が必要な場合に対して評価が見直され、ニーズに応じた柔軟な対応が可能となります。
【行動援護の基本報酬の見直し】
例: 支援時間が30分以上1時間未満の場合、407単位から437単位に増加。
一方で、長時間の支援(5時間30分以上6時間未満)については、1,940単位から1,904単位に減少。
特定事業所加算についても、強度行動障害者に対する医療機関や教育機関との連携要件が追加され、さらに「中核的人材養成研修」を修了した責任者の人数が評価の一部となります。
また、「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支援技術を必要とする「行動関連項目18点以上の者」を追加されることになりました。
この改定により、強度行動障害を有する人々が、より充実した支援を受けられる環境が整備され、地域生活の質が向上することが期待されます。事業所側も、新しい評価制度を活用し、専門性の高い支援を行うことが求められています。
Q&A VOL.2
上記に関してこれまで公表されたQ&Aを見ていきます。
(1)生活介護、施設入所支援
(重度障害者支援加算①)
問1 生活介護の重度障害者支援加算において、「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設における算定方法如何。
(答)
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
・ 生活介護を通所のみで利用している者については生活介護
・ 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援
においてそれぞれ算定することとなる。
(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)①)
問2 算定開始から 180 日以内の期間について初期加算を算定できるが、これは当該利用者が利用している日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。
(答)
お見込みのとおり。当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できる。
←請求に際しては利用状況を正確に確認する必要があります。(ブログ主)
(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)②)
問3 加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。
(答)
令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 180 日を経過していない場合は、(180 日-加算の算定を開始した日から令和6年3月 31 日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)における初期加算を算定する。
また、当該初期加算については、強度行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものであり、例えば、令和6年4月以前に改定前の重度障害者支援加算(Ⅱ)(区分4以上かつ行動関連項目 10 点以上)を算定して 180 日を経過していた区分6の者が、令和6年4月以降に改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ)(区分6以上かつ行動関連項目 10 点以上)を算定する場合は、初期加算の算定はできない。
なお、当該初期加算については、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とすることとしており、過去に重度障害者支援加算を算定していて退所した者が、再び同一事業所を利用することになった場合も、算定できない。
(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)③)
問4 生活支援員のうち 20%以上の基礎研修修了者を配置することとされているが、その具体的な計算方法如何。
(答)
前提として、常勤換算法方法で、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員を超える人員が配置されていることが必要である。
その上で、指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち 20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者であることとしているが、当該生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、従業者の実人数で算出し、非常勤職員についても員数に含めることとしている。
具体的な計算方法については、例えば、指定生活介護事業所に生活支援員として従事する従業者の人数が 12 名の場合、12 名×20%=2.4 名となり、よって、3名以上について研修を受講させる必要がある。
← 非常勤職員もカウントするため、チーム全体の研修修了者の割合に注意が必要です。(ブログ主)
(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)④)
問5 基礎研修修了者が勤務していない日であっても、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき、基礎研修を受講していない支援員が個別支援を行うことで算定できるのか。
(答)
算定できる。ただし、基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとしていることに留意すること。
←チームでの連携が重要で、記録管理に留意することが必要です。(ブログ主)
(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)⑤)
問6 行動関連項目 18 点以上の利用者を支援する場合の追加加算について、中核的人材養成研修修了者から助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成した場合でも算定可能としているが、当該中核的人材養成研修修了者の配置の要件如何。
(答)
中核的人材については、強度行動障害を有する利用者の特性の理解に基づき、環境調整、コミュニケーションの支援等について、支援従事者に対する適切な助言及び指導を通して、事業所におけるチーム支援をマネジメントする人材であるため、事業所等に常勤専従の職員として配置されることが望ましいが、人材の確保が困難な場合は、必ずしも常勤又は専従を求めるものではないとしており、他の事業所との兼務や非常勤職員であっても差し支えない。
なお、中核的人材養成研修修了者は、原則として週に 1 回以上、行動関連項目18 点以上である利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言及び指導を行うものとしているため、上記の場合であっても、適切に業務を遂行する体制を確保することが必要である。
←専従でなくても加算が認められるため、柔軟な運用が可能かと思われます。(ブログ主)
(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)⑥)
問7 行動援護従業者養成研修修了者が支援計画シート等を作成する場合であっても、加算は取得できるか。
(答)
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修については、いずれも平成 18 年厚生労働省告示第 538 号別表第8に定める内容以上の研修をいうものとしているため、いずれかの研修を修了した者であれば、求められる業務及び加算要件を満たすものである。
なお、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及び重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程についても、同告示別表第5に定める内容以上の研修をいうこととしており、同様である。
(2)短期入所
(重度障害者支援加算②)
問8 短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、算定の要件は何か。
(答)
短期入所の重度障害者支援加算の追加の加算については、通常の重度障害者支援加算を算定している場合に追加で加算を算定するものである。
このため、重度障害者支援加算(Ⅰ)においては、重度障害者等包括支援の対象者である障害支援区分6(障害児にあっては、障害児支援区分3)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、行動関連項目 10 点以上(障害児にあっては、障害児基準 20 点以上)である者、重度障害者支援加算(Ⅱ)については、区分4以上(障害児にあっては、障害児支援区分2以上)であって、行動関連項目 10 点以上(障害児にあっては、障害児基準 20 点以上)である者が対象となる。
その上で、当該利用者に対して、基礎研修修了者が、実践研修修了者が作成した支援計画に基づき支援を行った場合に追加の加算を算定できる。
また、行動関連項目 18 点以上(障害児にあっては、障害児基準 30 点以上)の利用者に対して、基礎研修修了者が、中核的人材養成研修修了者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき支援を行った日は、さらに追加の加算を算定できる。
なお、当該研修修了者については、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではない。
(3)共同生活援助
(重度障害者支援加算③)
問9 共同生活援助において、重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間に算定される初期加算が新設されたが、令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた者も算定できるか。
(答)
令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して 180日を経過している場合(令和6年3月 31 日が 180 日目となる場合を含む。)は、初期加算の算定はできない。
一方、加算を取得してから 180 日を経過していない場合は、(180 日-加算の算定を開始した日から令和6年3月 31 日までの日数)の期間について、初期加算を算定できる。
また、当該初期加算については、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とすることとしており、過去に重度障害者支援加算を算定していて退所した者が、再び同一事業所を利用することになった場合も、算定できない。
←開始からの経過日数に基づいて算定の可否が決まるため、しっかりとした確認が必要となります。(ブログ主)
(4)横断的事項
(重度障害者支援加算⑤)
問 10 重度障害者支援加算において、新たに行動関連項目 18 点以上の者への支援に対する評価が創設されたが、受給者証には当該加算の該当者であることが記載されることになるのか。
(答)
重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目 18 点以上の該当者であることについては、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。
←市町村への確認が必要な場合もあるため、適切な対応が必要となります。(ブログ主)
(中核的人材養成研修)
問 11 中核的人材養成研修について、令和9年4月以降の実施方法等はどのようになるのか。
(答)
中核的人材養成研修については、告示上、「強度行動障害を有する障害者等の特性の理解に基づき、障害福祉サービス事業を行う事業所又は障害者支援施設における環境調整、コミュニケーションの支援並びに当該障害者等への支援に従事する者に対する適切な助言及び指導を行うための知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表に定める内容以上のもの」としているが、研修の質を確保する観点から令和9年3月31日までの間は、のぞみの園が設置する施設が行う研修その他これに準ずるものとして厚生労働大臣が認める研修に限るとしているところである。令和9年4月以降の研修の実施方法等については、現在の研修の実施状況等を踏まえ引き続き検討し、令和8年度末までに改めて示すこととしている。
←今後の研修制度についても早めに情報を収集しておく必要があります。(ブログ主)
(集中的支援加算①)
問 12 広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成する際に利用者と生活環境のアセスメントを実施する場合にも集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるとされているが、具体的にはいつ請求するのか。
(答)
集中的支援開始後、速やかに請求するものとする。なお、この場合においても1月に4回の算定回数に含まれることに留意すること。
←迅速な請求手続きが必要となります。(ブログ主)
(集中的支援加算②)
問 13 集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していたサービスの支給決定や利用契約の取扱如何。
(答)
居住支援活用型の集中的支援を実施する場合で支給決定の変更が必要な場合や、新たな障害福祉サービス等の利用が必要となった場合は、支給決定自治体が必要な支給決定の手続きを進めることとなるが、当該加算においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、必要な支給決定を残しておく等、円滑なサービス利用を図ること。
また、例えば、共同生活援助を利用する利用者に施設入所支援を活用した居住支援活用型の集中的支援を実施する場合に、集中的支援実施期間中に、利用者の意に反して共同生活援助の利用契約を解除することはあってはならない。
←利用者が元の事業所に戻ることが基本であるため、必要な手続きがスムーズに進むように注意が必要です。(ブログ主)
(集中的支援加算③)
問 14 集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していた事業所等の役割如何。
(答)
居住支援活用型の集中的支援は、自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者に対して、居住の場を移して集中的支援を実施するものであり、当該児者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としている。
したがって、当該児者を受け入れて集中的支援を実施する施設・事業所が、広域的支援人材の指導援助の下でアセスメントや環境調整等に取り組むに当たっては、元の事業所等の職員も積極的に参画し、集中的支援の実施後に円滑に支援が再開できるよう、支援の内容を引き継いでいくことが重要である。
なお、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画においても、集中的支援実施報告書に基づく引き継ぎも含め、あらかじめ集中的支援終了後に当該児者が利用する事業所等への支援も記載し、円滑な引き継ぎ等を行うことが重要である。
(集中的支援加算④)
問 15 集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、広域的支援人材が集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合に、当該支援を行った日は加算(Ⅰ)の算定は可能か。可能である場合、訪問ではなくオンラインによる助言援助の場合でも可能か。
(答)
集中的支援実施計画に基づいて、居住支援活用型の集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合も算定可能である。
なお、居住支援活用型の集中的支援を活用する場合(加算(Ⅱ))においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画において、集中的支援実施報告書に基づく引き継ぎも含め、あらかじめ集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への支援も記載しておくこと。
また、加算(Ⅰ)の算定は、訪問又はオンラインを活用することを認めているので、オンラインによる助言援助の場合も算定可能である。
(集中的支援加算⑤)
問 16 集中的支援加算の算定期間終了後、再度、当該加算を活用して集中的支援を実施することは可能か。
(答)
集中的支援加算については、集中的支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り所定単位数を加算することとしており、この期間内に終了することが必要である。
ただし、何らかの事情により、その後も再び集中的支援の必要がある場合には、再度、集中的支援の実施に必要な手続きを踏まえて実施することは可能である。この場合、前回の実施報告書を基に関係者において十分に集中的支援の必要性について検討を行い、改めて集中的支援実施計画を作成の上で取り組むことが必要である。
←柔軟な取り扱いになっているようです。(ブログ主)
(集中的支援加算⑥)
問 17 広域的支援人材に加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か。
(答)
基本的には加算による額を広域的支援人材に支払うことを想定している。加えて、個別の状況によって必要な費用等が異なることから、加算による額を上回る額とすることは差し支えない。
=まとめ=
集中的支援加算など新設された加算は、Q&Aも含めたしっかりとした理解が必要です。誤請求が発生しないよう事前に内部での十分な周知が必要となります。
↓