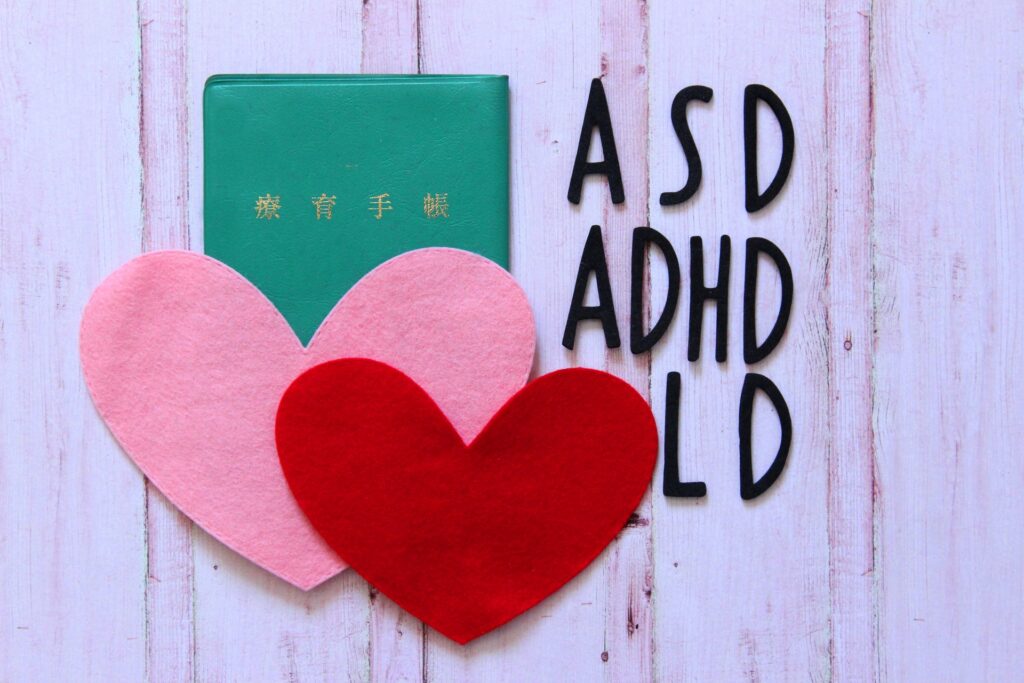
令和4年に設立された「こども家庭庁」のもと、令和5年に障害児支援がこども家庭庁に統合され、障害児施策については、地域全体での支援体制の整備が進められています。
こうした中、障害の有無にかかわらず、すべてのこどもが共に成長できる環境を作るという基本的な考え方のもと、児童発達支援や放課後等デイサービスについて、以下の大きな枠組みが提言されました。
提言概要
●「本人支援」「移行支援」「家族支援」「地域連携」に加え、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」といった5つの領域を含む総合的なものを基本とすること
●その上で、特定の領域に重点を置いた専門的支援が行われること
●ピアノや絵画など活動のみを提供する支援は、公費負担には適さない。提供する場合は、児童発達支援ガイドラインに示された支援の視点と結びつけて提供すること
●利用方法によって支援時間に違いがあるため、支援内容や人員配置にも注意し、支援時間を考慮した細やかな評価を行うことが必要
●保護者の預かりニーズについては、家族全体を支える観点から児童発達支援や放課後等デイサービスにおいても対応することが重要
●放課後等デイサービスでは、学校や家庭とは異なる、その子らしく過ごせる場としての機能が重要。不登校の障害児に対して関係機関と連携して支援していく必要があること
この枠組みを踏まえて、R6年度報酬改定では、児童発達支援、放課後等デイサービスについて大幅な見直しが行われましたので、以下、いくつかに分けてご紹介いたします。
1 総合的な支援の推進【児童発達支援、放課後等デイサービス】
支援を提供する事業所に対して、適切なアセスメント(評価)を行い、こどもの特性に基づいた支援を行うことが求められています。
具体的には、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」といった5つの領域すべてを含めた総合的な支援を提供することが基本です。
また、これらの領域と支援内容が個別支援計画にしっかり反映され、計画的に実施される必要があります。
2 支援プログラムの作成・公表【児童発達支援、放課後等デイサービス】
事業所は、5つの領域を明確に反映した支援プログラムを作成し、公表することが義務付けられました。
これにより、支援の内容を「見える化」することが進められています。なお、この義務が履行されない場合、報酬が減算される制度も導入されています(令和7年4月から適用)。
≪支援プログラム未公表減算【新設】≫
支援プログラム未公表減算 所定単位数の85%を算定
3 児童指導員等加配加算の見直し【児童発達支援、放課後等デイサービス】
児童指導員の加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験年数や配置形態に基づく評価に変更されました。これにより、経験豊富な人材がより評価され、専門職による支援が促進される仕組みになっています。
児童指導員等加配加算
[現行]
| 理学療法士等を配置 | 区分に応じて75~187単位/日 |
| 児童指導員等を配置 | 同 49~123単位/日 |
| その他の従業者を配置 | 同 36~ 90単位/日 |
↓
| 児童指導員等を配置 | 常勤専従・経験5年以上 区分に応じて75~187単位/日 常勤専従・経験5年未満 同 59~152単位/日 常勤換算・経験5年以上 同 49~123単位/日 常勤換算・経験5年未満 同 43~107単位/日 |
| その他の従業者を配置 | 同 36~ 90単位/日 |
※「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数
4 専門的支援加算・特別支援加算の見直し【児童発達支援、放課後等デイサービス】
理学療法士等の専門的な支援を強化するため、これまで別々に存在していた「専門的支援加算」と「特別支援加算」が統合されました。さらに、個別・集中的な専門的支援が計画的に行われる場合、2段階の加算が適用されるようになりました。
≪専門的支援加算・特別支援加算の見直し≫
○専門的支援加算
[現 行]
| 理学療法士等を配置 | 区分に応じて75~187単位/日 |
| 児童指導員等を配置 | 同 49~123単位/日 |
※専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合
○特別支援加算 54単位/回
※理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援加算を算定している場合は算定できない)
↓
[見直し後]
○専門的支援体制加算
区分に応じて49~123単位/日
・・・専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合
○専門的支援実施加算
150単位/回(原則月4回を限度)
・・・理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6回を限度)
※放課後等デイサービスの場合⇒専門的支援実施加算については、利用日数等に応じて月2回から最大月6回)
5 支援時間の評価と区分の新設【児童発達支援】
基本報酬の評価において、支援時間が細かく区分されるようになりました。
極めて短時間の支援(30分未満)は原則として算定対象外となり、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、「3時間超5時間以下」の3区分となりました。
5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行われます。
6 自己評価・保護者評価の充実【児童発達支援、放課後等デイサービス】
事業所は、1年に1回以上、自己評価と保護者評価を行い、その結果を公表することが義務付けられました。
≪運営基準【一部改正】≫
〇 指定児童発達支援事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項(※)について、従事者による評価を受けた上で、自ら評価を行うとともに、当該障害児の保護者による評価(保護者評価)を受けて、その改善を図らなければならない。
(※)体制整備の状況、従業員の勤務体制、関係機関との連携のための取り組みなど
〇 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
7 関係機関との連携強化と加算見直しについて【児童発達支援、放課後等デイサービス】
障害児支援の現場では、こどもと家族に対する包括的な支援が重要なことから、関係機関連携加算に新たに医療機関や児童相談所などが含まれました。また、個別支援計画作成時以外にも情報連携を行った場合の評価も加わりました。
関係機関連携加算の見直し内容
[現行]
関係機関連携加算(Ⅰ):200単位/回(月1回まで)
⇒ 保育所や学校との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成した場合
関係機関連携加算(Ⅱ):200単位/回(1回まで)
⇒ 就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
[見直し後]
関係機関連携加算(Ⅰ):250単位/回(月1回まで)
⇒ 保育所や学校との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して計画を作成した場合
関係機関連携加算(Ⅱ):200単位/回(月1回まで)
⇒ 保育所や学校との会議等で情報連携を行った場合
関係機関連携加算(Ⅲ):150単位/回(月1回まで)
⇒ 児童相談所や医療機関との会議等で情報連携を行った場合
関係機関連携加算(Ⅳ):200単位/回(1回まで)
⇒ 就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
セルフプランにおける事業所間連携の強化
セルフプランを利用して複数の事業所で障害児支援を行う場合に、事業所間でこどもの状態や支援状況を共有する際に評価される制度が新設されました。
また、自治体と事業所間で障害児支援利用計画や個別支援計画を共有し活用する仕組みも設けられ、さらなる情報共有が進められます。これにより、セルフプランを活用する家庭に対しても、より効果的で一貫性のある支援が提供されることが期待されます。
事業所間連携加算【新設】
事業所間連携加算(Ⅰ):500単位/回(月1回まで)
⇒ コーディネートの中心となる事業所が会議を開催し、事業所間で情報を連携し、家族への助言や自治体との情報連携も行った場合
事業所間連携加算(Ⅱ):150単位/回(月1回まで)
⇒ 他の事業所と会議に参画し、事業所内で情報を共有し、個別支援計画の見直しを行った場合
まとめ
以上、今回の改定の一部をご紹介しました。今回の改定は、報酬の見直しに加え、関係機関との連携強化を図ることで、こどもの特性やニーズに応じた支援を提供し、質の高い児童発達支援および放課後等デイサービスの実現を目指すものです。事業者の皆様には、新たな基準を十分にご確認いただき、引き続き適切な支援の提供に努めていただければと思います。
↓

