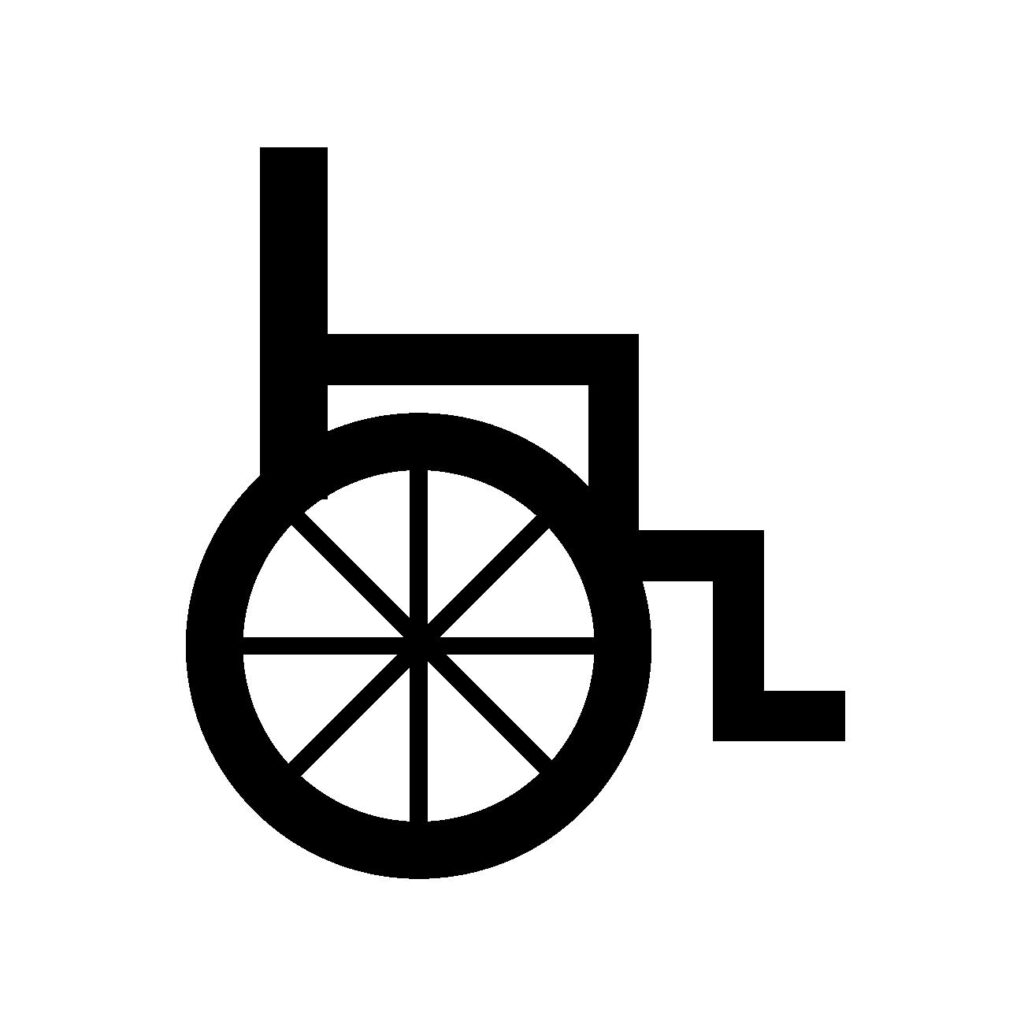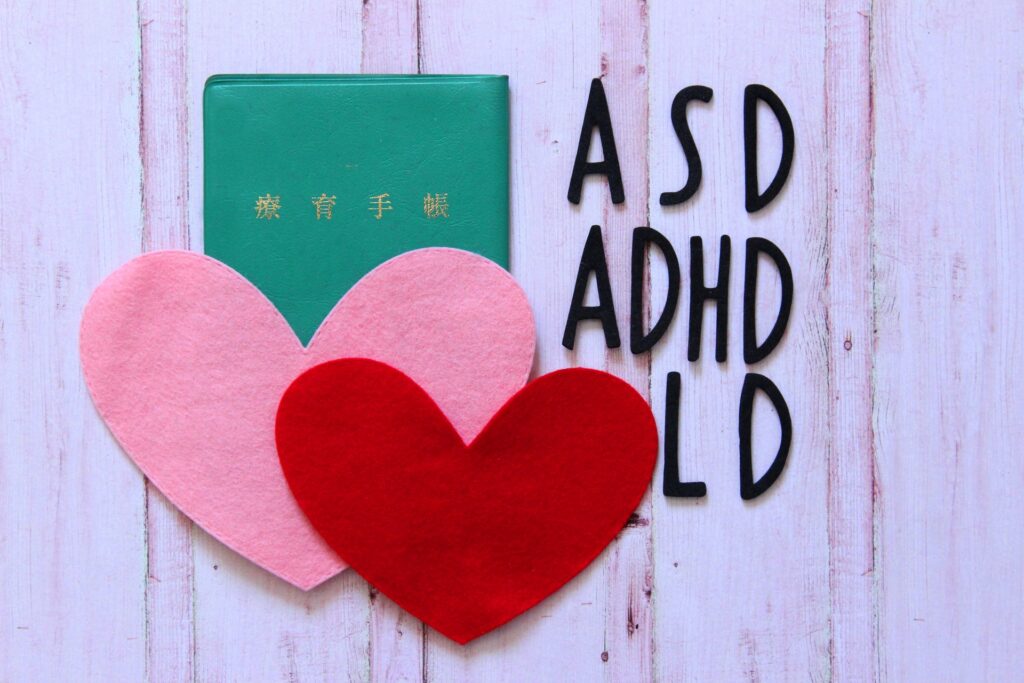今回の障害福祉サービス報酬改定において、新たに「就労選択支援」が公表されました。この制度は、令和7年10月から正式に開始される予定です。
本記事では、この新しい支援制度の背景と、制度の概要についてご紹介します。
現状と課題
就労系障害福祉サービスでは、これまで以下のような課題が指摘されてきました。
1 就労能力や適性の評価が確立されていない
就労系サービスを利用したいと考える障害者に対して、その就労能力や適性を評価する方法が確立されていない現状があり、障害者本人や支援者も、一般就労の可能性を十分に理解できていないことで、適切なサービスに繋げることが難しい状況にあること。
2 就労継続支援からの移行が難しい
一度、就労継続支援A型やB型を利用し始めると、その状況が固定されやすく、他の選択肢を考える機会が少なくなりがちであること。このため、障害者のキャリアの幅を広げるためのサポートが必要とされていること。
3 支援者の存在が職業生活を左右する
次のステップに進むための支援を行ってくれる人がいるかどうかで、障害者の職業生活や人生そのものが大きく左右されることがあること。適切な支援者がいれば、障害者のスキルアップや就労移行がスムーズに進む一方で、そうでない場合は、現状に留まり続ける可能性が高まること。
4 専門的支援体制の課題
サービスの利用前には、専門的な支援体制が十分に整っていないことが多く、アセスメントを実施しても、その結果をその後の働き方や就労先の選択に十分活かせていない現状があること、また、サービスを利用した後も、障害者の就労ニーズや能力が変化しているにもかかわらず、他の選択肢を積極的に検討する機会が限られていること。
就労選択支援とは?
このような背景を踏まえて、今回の改定では「就労選択支援」という新しい制度が導入されることになりました。
この制度は、障害者が自分の働き方を考えるためのサポートを提供し、就労継続支援を利用して、就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等、適正にあった選択肢を提供することを目的としています。
就労選択支援の内容
以下に、就労選択支援の内容についてご紹介します。
1 サービス対象者
対象者は以下の通りです。
〇就労継続支援B型を利用する前の障害者
原則として、就労選択支援を利用することが義務づけられます(令和7年10月以降)。これにより、障害者が自分の就労適性や選択肢を考えた上で就労継続支援B型を利用できるようになります。
〇新たに就労継続支援A型を利用する意向がある障害者、および就労移行支援を標準利用期間を超えて利用したい障害者
令和9年4月以降、これらの利用者も原則として就労選択支援を利用することが求められます。この仕組みにより、就労継続支援A型の利用や就労移行支援の延長利用を希望する方が、より適切な支援を受けながら次のステップを検討できるようになります。
2 実施主体
就労選択支援を提供する事業者には、以下の要件が求められます。
〇過去3年以内に3人以上の利用者を、通常の事業所に新たに雇用した実績がある就労移行支援事業者または就労継続支援事業者
これにより、実績のある事業者が対象となり、信頼性の高い支援が提供されることが保証されます。
〇障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める、障害者支援の経験・実績がある事業者
具体例として、次のような事業者が該当します。
・就労移行支援事業所
・就労継続支援事業所
・障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
・自治体が設置した就労支援センター
・人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)に基づく訓練事業を行う機関
など
3 就労選択支援事業者の努力義務
就労選択支援事業者には、以下のような取り組みが求められます:
〇自立支援協議会への定期的な参加
自立支援協議会に定期的に参加し、地域の福祉サービスや就労支援に関する課題やニーズについて協議を行い、連携体制を強化することが求められます。
〇公共職業安定所(ハローワーク)への訪問
地域における雇用に関する情報を収集し、それを利用者の進路選択に役立てるよう努めることが求められます。
これらの取り組みを通じて、事業者は地域における就労支援の社会資源を最大限に活用し、利用者に対して適切な進路選択に資する情報提供を行うことが期待されています。
4 人員配置の基準
就労選択支援事業所には、以下の人員配置が求められます。
〇専従の就労選択支援員の配置
各事業所ごとに管理者を配置し、さらに、常勤換算で利用者数を15で割った人数以上の専従の就労選択支援員を配置することが必要です。
〇兼務の許可
就労選択支援を就労移行支援や就労継続支援と一体的に行う場合には、移行支援や継続支援の職員や管理者が就労選択支援員を兼務することが可能です。
この際、利用者数の合計がそれぞれの支援の利用定員を超えないようにする必要があります。
5 就労選択支援員の要件
就労選択支援員として働くためには、以下の要件を満たす必要があります:
〇就労選択支援員養成研修の修了
就労選択支援員になるには、必ず「就労選択支援員養成研修」を修了していることが要件となります。
<経過措置について>
就労選択支援員養成研修が始まってから最初の2年間は、基礎的な研修を修了している者や、それと同等以上の研修を受けた者も、就労選択支援員として認められる経過措置が設けられています。
〇就労選択支援員養成研修の受講要件
この「就労選択支援員養成研修」を受講するためには、すでに「基礎的研修」を修了していることや就労支援に関して一定の経験があることが受講の条件とされています。
<当面の措置>
令和9年度末までの間は、現行の就労アセスメントの実施などに関して一定の経験があり、かつ基礎的研修と同等以上の研修を修了している者も、研修を受講できるようにする特例措置が取られます。
〇個別支援計画の作成やサービス管理責任者配置は不要
就労選択支援では、個別支援計画の作成は不要とされています。また、サービス管理責任者の配置も求められません。事業者は柔軟に支援を提供できる仕組みが整えられています。
6 就労選択支援の基本プロセス
就労選択支援の提供にあたっては、事業者が段階的かつ計画的に支援を進めていくことが求められます。
〇アセスメントの実施
就労選択支援事業者は、短期間の生産活動やその他の活動を通じて、利用者の「就労に関する適性、知識及び能力の評価」を行います。また、利用者がどのような働き方を望んでいるのか、「就労に関する意向等の整理」も実施します。
〇多機関連携会議の開催
アセスメントの結果をまとめる際には、多機関連携会議を開催します。この会議では、利用者の就労に関する意向を改めて確認し、より適切な支援を検討します。
<多機関連携会議のメンバー例>
・利用者本人
・市町村の担当者
・指定特定相談支援事業者
・公共職業安定所(ハローワーク)の関係者など
これにより、多方面から利用者をサポートし、最適な就労支援を提供できる体制が整えられます。
〇関係機関との連携・調整
事業者は、必要に応じて関係機関との連絡調整を行います。
〇地域の社会資源の活用
事業者は、地域における就労支援に関連する社会資源や雇用に関する事例の収集に努め、利用者に対して就労に関する選択肢を提供します。
7 支給決定期間
就労選択支援を受ける際の支給決定期間は、次のように定められています:
〇原則1か月の支給決定
基本的には、支給決定期間は1か月とされています。しかし、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支給決定を行うことができます。
〇アセスメント期間は2週間以内が基本
就労選択支援の重要な要素であるアセスメントの実施期間は、基本的に2週間以内とされています。
8 特別支援学校における取扱い
特別支援学校に通う生徒に対しても、就労選択支援は活用することができます。ポイントは以下のとおりです。
〇高等部の各学年で実施可能
特別支援学校の高等部では、就労選択支援を各学年で実施することが可能です。生徒が早い段階から自分の就労適性や希望を確認し、進路について具体的に考える機会を得られるようにするためです。
〇複数回の実施が可能
在学中に、就労選択支援を複数回受けることも可能です。これは、生徒が成長や状況の変化に応じて、再度評価を受けることで、より適切な進路選択ができるようにするためです。
〇職場実習との連携
特別支援学校で実施される職場実習のタイミングでも、就労選択支援を活用することを可能とし、実習中に得た経験を基に、具体的な進路や職場選択についてサポートを受けることができます。
9 他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い
就労選択支援のアセスメントに関しては、他の機関が実施した同様の評価を活用することもできます。具体的には次のような場合が該当します:
〇他機関のアセスメントを活用できる場合
障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、あるいは就労系障害福祉サービス事業所が、就労選択支援で行うアセスメントと同様の評価や整理を実施した場合は、それをもってアセスメントの代わりとすることができます。重複したアセスメントの実施を避けることで利用者の負担を軽減し、効率的に支援を行うためです。
10 中立性の確保
就労選択支援事業においては、一定の事業者が利用者を抱え込むことがないよう、中立性が確保されることが重要です。以下の方策が提示されております。
〇自法人への誘導を防ぐための対策
就労選択支援事業所が、自法人が運営する就労系障害福祉サービスへ利用者を誘導しないよう、次のような措置が取られます。
・アセスメント結果のチェック
就労選択支援事業所において実施したアセスメントの結果(前6カ月)により、利用者が利用した就労移行支援、A型、B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたもの割合が100分の80を超えている場合には減算されます。
・減算の適用除外
ただし、地域によっては利用可能な事業所が1カ所しかないなど、特定の事業所を利用せざるを得ない場合は、正当な理由があると見なされ、この減算は適用されません。
・減算の詳細
特定事業所集中減算【新設】・・・200単位/月の減算が適用されます。
〇中立性を確保するためのその他の方策
中立性をさらに強化するために、以下の方策も導入されます。
・支給決定の適正化
市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領で示されます。
・金品の受領禁止
就労選択支援事業者は、他の障害福祉サービス事業者やその従業者から利用者やその家族を紹介する対価として、金品や財産上の利益を受け取ることが禁止されております。
・多機関連携会議の開催
利用者に提供する情報に誤りや偏りがないよう、就労選択支援事業者は多機関連携会議を開催し、公正性を担保します。
11 計画相談支援事業との連携・役割分担
就労選択支援事業では、計画相談支援事業との連携が重要な役割を果たしています。就労選択支援事業者、就労移行支援事業者、相談支援専門員の役割分担は以下のようになります。
〇アセスメント結果の提供義務
就労選択支援事業者は、アセスメントを実施し、その結果を作成した際には、利用者自身および指定された特定相談支援事業者に提供しなければなりません。
〇就労移行支援事業者等による情報共有
就労移行支援事業者等は、計画相談支援を行う者と連携し、利用者に対して定期的に就労選択支援に関する情報提供を行う必要があります。
〇相談支援専門員の役割
・相談支援専門員は、利用者が就労移行支援や継続支援を利用している場合に、その支援が適切かどうかをモニタリングします。その結果、就労選択支援の利用が必要と判断された場合には、就労移行支援や継続支援を提供する事業者と連携して、利用者に対して就労選択支援に関する情報を提供します。
・サービス利用計画の見直し
利用者が就労選択支援を受けている場合、アセスメントの結果を基にサービス等利用計画の見直しを行います。この際、就労選択支援事業者と緊密に連携し、必要な情報の提供と助言、地域の関係機関と連絡調整を行わなければなりません。
12 基本報酬・加算の設定
〇就労選択支援サービス費【新設】
1,210単位/日
〇加算と減算の設定
就労選択支援においては、基本報酬に加えて、以下の条件を満たす場合に加算・減算が適用されます。
<加算>
・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
・高次脳機能障害者支援体制加算
・利用者負担上限額管理加算
・食事提供体制加算
・福祉専門職員配置等加算
・欠席時対応加算
・医療連携体制加算
・送迎加算
・在宅時生活支援サービス加算
・福祉・介護職員等処遇改善加算
<減算>
・虐待防止措置未実施減算
・身体拘束廃止未実施減算
・業務継続計画未策定減算
・情報公表未報告減算
まとめ
就労選択支援は、障害者が自分に合った働き方を見つけ、就労の選択肢を広げるために設けられた新しい制度です。
この支援では、アセスメントや多機関連携を通じて、利用者一人ひとりに対して適切なサポートが提供されます。本人の希望や能力をしっかりと把握し、適正にあった選択を支援することが、この制度の大きな目的です。
↓