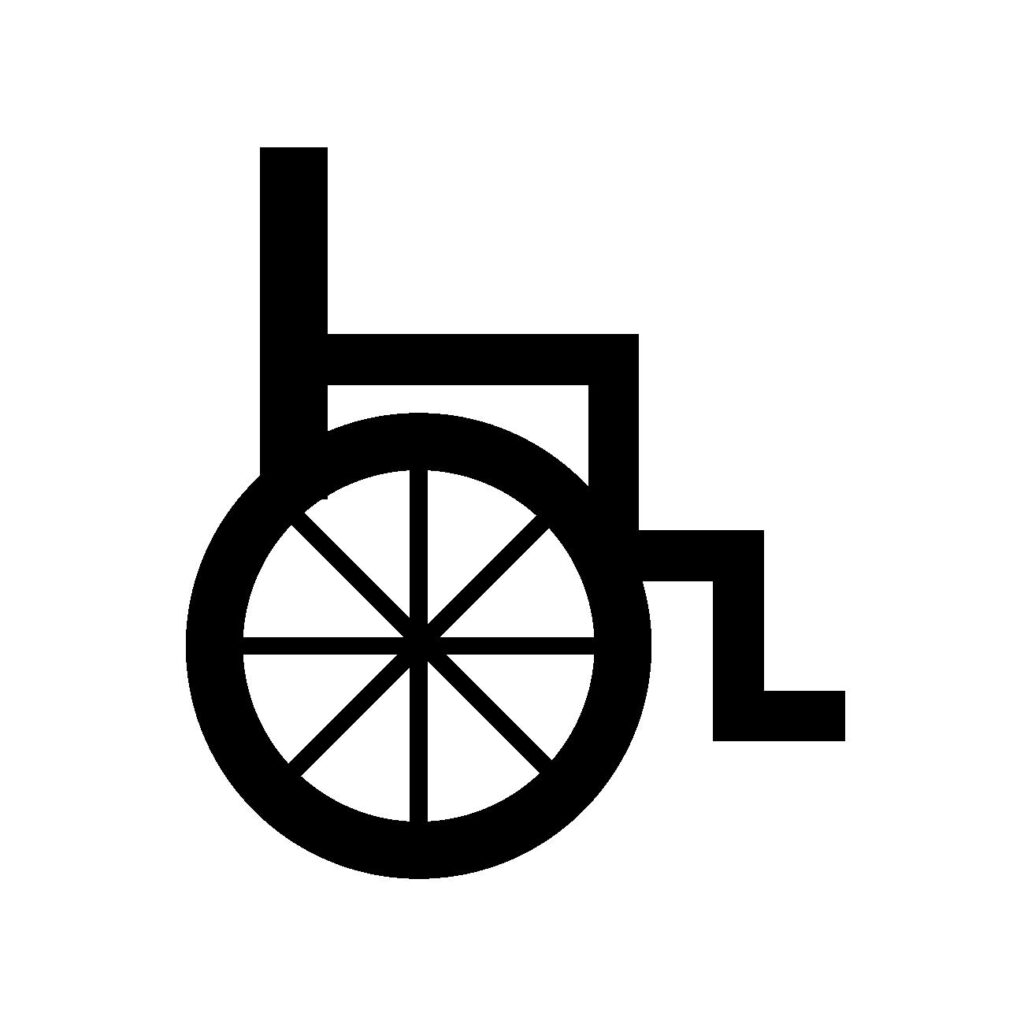障害者の一般就労への移行や就労支援施策が着実に進展している中で、さらに障害者の就労を支援するため、事業の安定的、効率的な実施、生産活動収支や工賃の改善について見直しが行われました。以下、ご紹介します。
1 就労移行支援
就労移行支援では、特別支援学校からの直接就職者の増加や、特に地方における利用者数の減少が顕著であり、定員削減の方向での議論が進んでいました。また、支援計画の作成においては、サービス管理責任者が必ずしも出席せずとも、他の支援員が地域のノウハウを活用することで、効果的な支援が実現できるのではないかという議論がありました。
今回の見直しでは、就労移行支援事業所の利用定員規模と支援計画会議実施加算に関する重要な変更が行われましたので、ご紹介します。
ア 就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し
従来、就労移行支援事業所は、利用者が20人以上(離島などの特例では10人以上)の規模とされてきましたが、小規模事業所の運営を促進し、地域における多様な支援ニーズに応えるため、10人以上であれば事業所の運営が可能なように見直されました。
現行制度:20人以上
新制度:10人以上
イ 支援計画会議実施加算の見直し
支援計画会議の実施において、これまでは、サービス管理責任者が会議に参加することが必須とされておりましたが、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とされました。
なお、地域のノウハウを活用して支援効果を高める加算であることから、加算の名称を地域連携会議実施加算に変更することになりました。
地域連携会議実施加算(Ⅰ):サービス管理責任者が出席した場合 583単位/回
(1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度)
地域連携会議実施加算(Ⅱ):サービス管理責任者以外の職業指導員、生活支援員、就労支援員が出席し当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合 408単位/回
(1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度)
※ 算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月につき1回かつ1年につき4回を限度とする。
2 就労継続支援A型の報酬見直しについて
就労継続支援A型事業所の基本報酬は、従来から「労働時間」や「生産活動」などの評価項目によるスコア方式で算定されており、全体の8割以上の事業所が200点満点中105点以上を取得していました。しかし、さらなる経営改善を促し、一般就労への移行を支援するための取り組みを反映する必要があるとの議論がなされ、今回の見直しが実施されたところです。
今回の見直しでは、以下のような項目が変更され、スコア方式の評価に加えて、情報公表制度におけるスコアの公表が新たに導入されました。
ア 労働時間の評価
平均労働時間が長い事業所には、より高いスコアが付与されるようになりました。これにより、労働時間を確保する事業所がより高く評価されます。
現行:5点~80点
見直し後:5点~90点
イ 生産活動の評価
生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点され、下回った場合には減点される仕組みに変更されました。これにより、生産活動の成果をより明確に反映させることができます。
現行:5点~40点
見直し後:-20点~60点
ウ その他の評価項目
「多様な働き方」や「支援力向上」の評価スコアはそれぞれ引き下げられ、より重点的な評価が行われるように調整されています。また、新たに「経営改善計画」と「利用者の知識及び能力向上」の項目が追加され、これらの取り組みに対しても評価が行われます。
多様な働き方:0点~35点 → 0点~15点
支援力向上:0点~35点 → 0点~15点
経営改善計画(経営改善計画の作成状況により評価)【新設】):-50点~0点
利用者の知識及び能力向上(利用者の知識及び能力の向上のための支援の取組状況により評価)【新設】:0点~10点
3 B型就労継続支援の報酬体系見直しについて
B型就労継続支援事業所の報酬体系は、これまで平均工賃月額に基づいて評価されてきましたが、よりメリハリをつけた評価や、「利用者の就労や生産活動への参加状況」による報酬体系の見直しが必要であること、目標工賃達成指導員の配置による成果を適切に評価すべきこと、さらに、多様な利用者に対応する事業所の評価方法を見直すべきとの議論が行われてきました。これらを踏まえ、以下のように報酬体系が見直されることとなりました。
ア 平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し
工賃向上を促進するため、平均工賃月額が高い事業所の報酬単価を引き上げ、低い事業所は引き下げられることになりました。
イ 「利用者の就労や生産活動への参加状況」の報酬体系の見直し
「利用者の就労や生産活動への参加状況」の報酬体系について、利用者の利用時間が4時間未満の割合が5割以上の場合、基本報酬が減額されます。
≪短時間利用減算【新設】≫
(「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系)
所定の単位数の70/100算定
←算定利用時間が4時間未満の利用者が全体の5割以上である場合には、基本報酬が減算されます。ただし、個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合、又は短時間利用となるやむを得ない理由がある場合は利用者数の割合の算定から除外されます。
ウ 目標工賃達成指導員配置加算の見直し
また、目標工賃達成指導員の配置加算の要件も見直され、実際に工賃を向上させた場合に加算が適用される仕組みとなっています。
≪目標工賃達成指導員配置加算の見直し≫(「平均工賃月額」に応じた報酬体系)
[現 行]
○ 目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、「職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上」をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に加算する。
[見直し後]
目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、「職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上」をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に加算する。
その上で単位数は以下のとおりに変更となります。
利用定員 報酬単価
20人以下 89単位⇒45単位
21人以上40人以下 80単位⇒40単位
41人以上60人以下 75単位⇒38単位
61人以上80人以下 74単位⇒37単位
81人以上 72単位⇒36単位
≪目標工賃達成加算【新設】≫(「平均工賃月額」に応じた報酬体系)
10単位/日
目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算されることになりました。
エ 平均工賃月額の算定方法の見直し
事業所によっては、障害特性により利用日数が少ない利用者が多い場合もあります。このため、新たな算定式が導入され、前年度の開所日1日当たりの平均利用者数に基づいて平均工賃月額が算定されるようになりました
[現 行]
① 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ウ)により1人当たり平均工賃月額を算出
※ ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
←上記①については、下記②、③↓の例外が認められておりました。
②以下の場合は、平均工賃月額の算出から当該月の工賃支払対象者から除外し、当該月に当該利用者に支払った工賃は工賃総額から除外して算出。
・ 月の途中において、利用開始又は終了した利用者
・ 月の途中において、入院又は退院した利用者
・ 月の途中において、全治1か月以上の怪我やイ流行性疾患により連続1週間以上利用できなくなった利用者
③ また、以下の場合は、事業所の努力によっても利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、工賃支払対象者・工賃総額から除外して算出。
・ 複数の日中活動に係る障害福祉サービスの利用者
・ 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある利用者
改定後、算出方法は以下のとおりです。
[見直し後]
前年度の平均工賃月額の算定方法は以下の通り。
ア 前年度における工賃支払総額を算出
イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出
※ 現行の②・③の算定方法は廃止
4 就労定着支援の見直しについて
今回の見直しでは、就労定着支援事業所の報酬体系や支援体制の改善が図られました。利用者数に応じた報酬体系ではなく、就労定着率を基準とした報酬制度が導入され、ケース会議の出席者についても柔軟な対応が認められるようになりました。
ア 就労定着率に基づく報酬体系
従来は利用者数に基づいていた報酬体系が、今回の見直しにより就労定着率のみを基準とする報酬体系に変更されました。
イ 地域連携会議実施加算の見直し
地域の就労支援機関と連携して行うケース会議において、サービス管理責任者以外の就労定着支援員が出席した場合でも、加算が適用されるようになりました。
地域連携会議実施加算(Ⅰ):サービス管理責任者が出席する場合 579単位/回
(1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度)
地域連携会議実施加算(Ⅱ):サービス管理責任者以外の就労定着支援員が出席し、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合 405単位/回
(1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度)
※ 算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月につき1回かつ1年につき4回を限度とする。
ウ 支援終了時の対応について
≪支援体制構築未実施減算【新設】≫
就労定着支援の終了後も支援が必要とされる利用者に対して、適切な引き継ぎ体制が構築されていない場合、支援体制構築未実施減算が新たに設けられました。この場合、所定単位数の10%が減算されます。
・ 要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共有に係る指針の策定・責任者の選任
・ 要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共有の状況に係る記録の作成及び保存
エ 実施主体の追加
新たに障害者就業・生活支援センターが、就労定着支援事業の実施主体に追加されました。
オ 就労移行支援事業所等との一体的な運営
今回の見直しでは、就労移行支援事業所等との一体的な運営が推進されました。これにより、就労移行支援事業所の職業指導員などが就労定着支援に従事した時間を、常勤換算の勤務時間に算入することが可能となりました。
5 就労系障害福祉サービスにおける横断的な改定事項について
今回の改定では、就労系障害福祉サービスにおける評価方法や支援体制の見直しが実施されました。特に、利用者の支援に関する柔軟な対応や事務処理の簡素化が進められています。以下、主な改定内容をご紹介します。
ア 就労継続支援の一時的利用する際の評価【就労継続支援A型・B型】
一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際、就労継続支援A型・B型の報酬算定において、その労働時間や工賃は計算から除外されることになりました。
イ 休職期間中の利用条件の見直し【就労移行支援・就労継続支援A型・B型・生活介護・自立訓練】
一般就労中の障害者が休職期間中に就労系サービスを利用する際、復職支援の実施が見込めない場合等の現行の利用条件や、一般就労中の障害者が休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する際の条件について、改めて事務連絡で周知されるとともに、支給申請の際に、当該障害者の雇用先企業や主治医の意見書等の提出が必要とされます。
ウ 施設外就労に関する実績報告書の廃止【就労移行支援及び就労継続支援A型・B型】
地方公共団体の事務負担軽減のため、施設外就労に関する実績報告書の毎月の提出義務が廃止されました。ただし、事業所には記録の作成・保存義務があり、必要に応じて地方公共団体が確認できるようにする必要があります。
エ 基礎的研修開始に伴う対応【就労移行支援及び就労定着支援】
今後、就労支援員や就労定着支援員は基礎的研修(令和7年度から開始)の受講が必須となります。ただし、令和9年度までは経過措置が置かれます。
オ 施設外支援に関する事務処理の簡素化【就労移行支援及び就労継続支援A型・B型】
施設外支援に関しては、これまで1週間ごとに個別支援計画の見直しが必要でしたが、改定後は1ヶ月ごとの見直しが行われている場合に報酬を算定できるようになりました。
以下にこれまで公表されているQ&Aをご紹介します。
Q&A VOL.1
就労継続支援B型
(短時間利用減算)
問 57 短時間利用減算の具体的な計算方法如何。また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。
(答)
就労継続支援 B 型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いと同様であるので、以下 Q&A の問 49 から問 52 を参照いただきたい。その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)
以下、「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)生活介護 問49~問52を引用↓
生活介護
(短時間利用減算①)
問4 9 前3月における事業所の利用者のうち、事業所の平均利用時間が5時間未満の利用者のしめる割合は、具体的にどのように算出するのか。
(答)
以下の方法により、算出した割合が 100 分の 50 以上である場合に、短時間利用減算を適用する。
① 各利用者について、前3月における利用時間の合計時間を、利用日数で除して、利用日1日当たりの平均利用時間を算出する。
② 当該月における、①により算出した平均利用時間が5時間未満の利用者の延べ人数を、事業所の利用者の延べ人数で除する。
(短時間利用減算②)
問5 0 重度の身体障害者や精神障害者は、障害特性や症状、通院や起床介護などの生活パターンなどの理由で、5時間未満の利用になってしまう場合があるが、そのような利用者についても、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定に含むのか。
(答)
例えば、重度の身体障害や精神障害等、障害特性等に起因するやむを得ない理由により5時間未満の利用になってしまう利用者については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除いて差し支えない。
なお、やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案された上で、サービス担当者会議において検討され、サービス等利用計画等に位置付けられていることが前提であり、市町村においては当該計画等を基に判断されたい。
(短時間利用減算③)
問5 1 利用時間については、送迎のみを実施する時間は含まれないとされているが、遠方からの利用者で送迎に長時間を要する利用者についても、送迎に要する時間は利用時間に含めないのか。
(答)
遠方からの利用者等、やむを得ず送迎に長時間を要する利用者については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除いても差し支えない。
(短時間利用減算④)
問5 2 土曜日やイベントの日など、特例的に短時間の開所としている日については、利用者全員が5時間未満の利用となるが、これらの日についても利用時間の算定に含むのか。
(答)
運営規程に営業時間を明示した上で、特例的に短時間開所の日を設けている場合等については、平均利用時間の算定から外すなど柔軟な取扱いとして差し支えない
(目標工賃達成加算)
問 58 目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。
(答)
目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。
ア 指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合
イ 当該工賃目標が当該工賃目標の対象となる年度(以下「目標年度」という。)の前年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、目標年度の前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と目標年度の前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上である場合
具体的には、以下の両要件をともに満たす場合に加算の対象となる。
・要件1:①≧③+(④-⑤)となっていること(※④-⑤が0未満の場合は、0として計算)
・要件2:②≧①となっていること
① 工賃向上計画における工賃目標
② 目標年度の事業所の平均工賃月額(実績)
③ 目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額(実績)
④ 目標年度の2年度前における全国平均工賃月額
⑤ 目標年度の3年度前における全国平均工賃月額
就労定着支援
(支援体制構築未実施減算)
問 59 就労定着支援の支援体制構築未実施減算について、「支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者」であるかの判断はどのように行うのか。
(答)
基本的には、就労定着支援事業所が支援を行っていく中で判断していくこととなるが、利用者本人の状況、雇用先企業及び連携先の関係機関等の助言を十分踏まえること。
Q&A VOL.2
就労継続支援B型
(平均工賃月額の算定方法)
問 24 今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃
月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。
また、算出に当たっての1日あたりの平均利用者数や平均工賃月額の小数点の取扱について、どのようにすればよいか。
【見直し後の平均工賃月額の算定方法】
ア 前年度における工賃支払総額を算出
イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出
(答)
開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバザー等の行事で利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、開所日として算定して差し支えない。
また、「前年度における開所日1日あたりの平均利用者数」の小数点の取扱については、小数点第1位までを算出する。小数点第2位以降もある場合は小数点第2位を切り上げるものとする。
例:14.679人の場合⇒14.7人
加えて、平均工賃月額の小数点については、円未満を四捨五入する。
(目標工賃達成加算)
問 25 目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃額を指すのか。
(答)
お見込みのとおり。
なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上であることが要件となる。
そのため、目標工賃達成加算の要件を満たすために、工賃向上計画を修正する必要がある場合は、計画期間の途中であっても修正して差し支えない。
Q&A VOL.3
就労継続支援 B 型
(目標工賃達成加算の取扱いについて )
問 13 目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算を算定できるということか。
(答)
貴見のとおり。目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。
(目標工賃達成加算)
問 58 目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。
(答)
目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。
ア 指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合
イ 当該工賃目標が当該工賃目標の対象となる年度(以下「目標年度」という。)の前年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、目標年度の前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と目標年度の前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上である場合
具体的には、以下の両要件をともに満たす場合に加算の対象となる。
・要件1:①≧③+(④-⑤)となっていること(※④-⑤が0未満の場合は、0として計算)
・要件2:②≧①となっていること
① 工賃向上計画における工賃目標
② 目標年度の事業所の平均工賃月額(実績)
③ 目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額(実績)
④ 目標年度の2年度前における全国平均工賃月額
⑤ 目標年度の3年度前における全国平均工賃月額
なお、加算が算定できるケースの具体例については、以下の(例1)及び(例2)を参照されたい。
(例1:令和5年度の実績に係る加算を令和6年度に算定する場合)
令和4年度における事業所の平均工賃月額(実績)が 17,000 円であった場合、17,731 円以上の額を工賃目標として立て、当該工賃目標を達成した場合に加算の算定が可能。
(例2:令和6年度の実績に係る加算を令和7年度に算定する場合)
令和5年度における事業所の平均工賃月額(実績)が 17,500 円であった場合、18,024 円以上の額を工賃目標として立て、当該工賃目標を達成した場合に加算の算定が可能。
↓