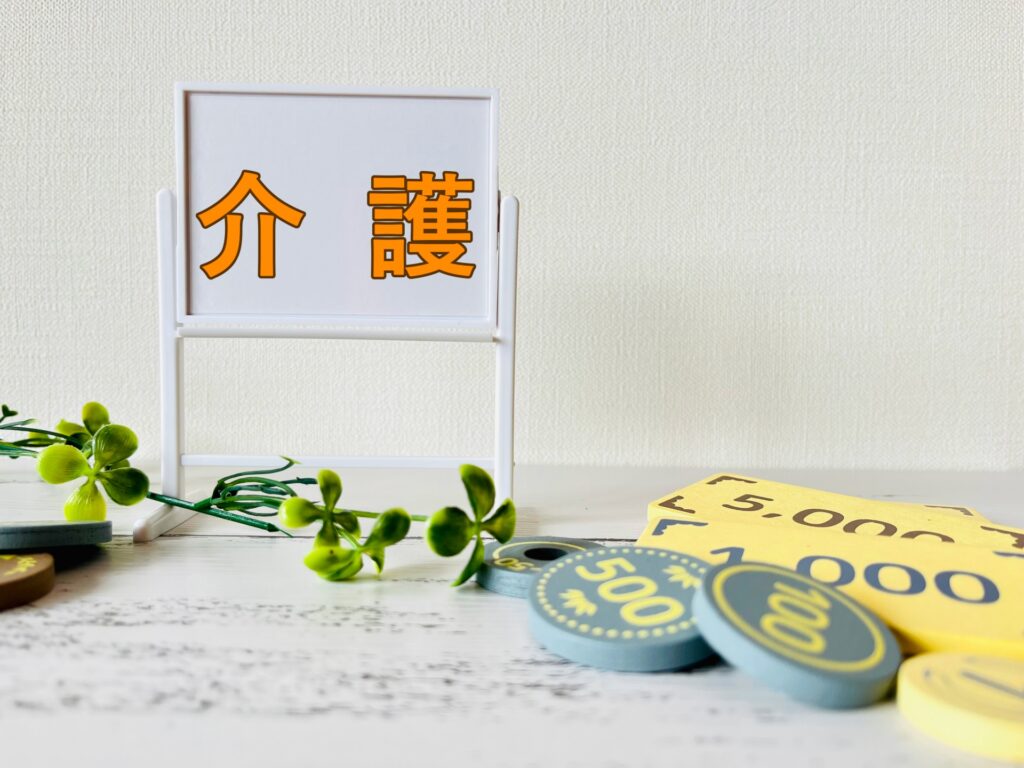
総合マネジメント体制強化加算とは、地域密着型サービス事業者を対象に、日々の多職種との連携や地域との連携、そのほか環境の変化に合わせて計画を見直した場合に、その業務を評価する加算になります。
対象となる異業者は、地域密着型のサービスで、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護(予防を含む)、看護小規模多機能型居宅介護となります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護について、地域包括ケア推進と地域共生社会実現への貢献度を評価する新たな区分を設け、より地域に開かれた拠点としての役割を強化し、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進します。
新しい算定要件
新設される算定要件は以下のとおりです。
| 算定要件(新設分のみ) | 小規模多機能型居宅介護 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
| (4)日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること | ○ | ○ | ○ |
| (5)必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービ スを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること | ○ | ○ | ○ |
| (6)地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること | 事業所の特性に応じて(6)~(9)について1つ以上実施 | 事業所の特性に応じて(6)~(9)について1つ以上実施 | ○ |
| (7)障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること(※) | 事業所の特性に応じて(7)~(10)について1つ以上実施 | ||
| (8)地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること | |||
| (9)市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること | |||
| (10)地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること | ― | ― |
(※)定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。」が要件。
従前は、以下の3要件だけで1,000単位が認められておりましたが(サービス種別で若干の違いアリ)、今回の改定により、従前の3要件だけの場合は800単位まで引き下げられました。
=3要件=
(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること
(2)利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること
(3)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること
この3要件に加え、新設された算定要件を実施することで1,200単位の加算が認められることになりました。
地域包括ケア、地域共生社会への具体的な貢献を求めてきた現れと捉えることができると思われます。
Q&A VOL.1
<R6年度Q&A>
今回の訪問介護の特定事業所加算の改正についてQ&Aを見てみます。
問 145 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること」とされているが、具体的な取組頻度についてどのように考えればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。
(答)
・ 地域住民等からの相談への対応は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、常に地域住民等からの相談を受け付けられる体制がとられていれば、当該要件を満たすものである。
・ また、日常的に利用者と関わりのある地域住民等からの相談が行われやすいような関係を構築していることも重要である。
・ なお、地域住民等からの相談が行われていることは、日々の相談記録等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成することは要しない。
←地域住民等からの相談に対しては、特定の頻度で対応する必要はなく、常に相談を受け付けられる体制を整えていることが重要のようです。地域住民との信頼関係を築き、気軽に相談ができる環境を作ることが求められています。相談があった場合は、日常的な記録で確認できれば問題ないため、新たな書類作成は不要のようです。(ブログ主)
問 146 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
(答)
・ 具体的な取組内容については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 18 年3月 31 日老計発第 0331005 号、老振発第 0331005号、老老発第 0331018 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)第2の5(12)において、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」の例をお示ししている。
・ ただし、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において、一定の理解・評価を得て、地域の中で核となり、地域資源を効果的に活用し利用者を支援する取組は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられるため、当該通知に例示する以外の取組も該当し得る。
・ また、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」については、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続するために、利用者一人一人にとってどのような支援が必要かということについて、地域住民等と連携した上で、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。
←地域の資源を活用して利用者を支援することが求められていますが、その具体的な内容は地域ごとに異なります。各事業所が地域の実情に応じて柔軟に取り組むことが重要で、一定の頻度に縛られるものではないとされております。利用者一人ひとりに必要な支援を常に考え、地域住民と連携しながら取り組んでいれば、要件を満たすとされています。ただ、難しいですよね。(ブログ主)
問 147 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)における「地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同での事例検討会、研修会等」については、市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。
(答)
・ 貴見のとおりである。
・ ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず地域住民や民間企業、他の居宅サービス事業者など複数の主体が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、これらの複数の主体が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である。
←複数の関係が参画することで、地域全体でのケアの質向上が図られるという趣旨です。(ブログ主)
↓
