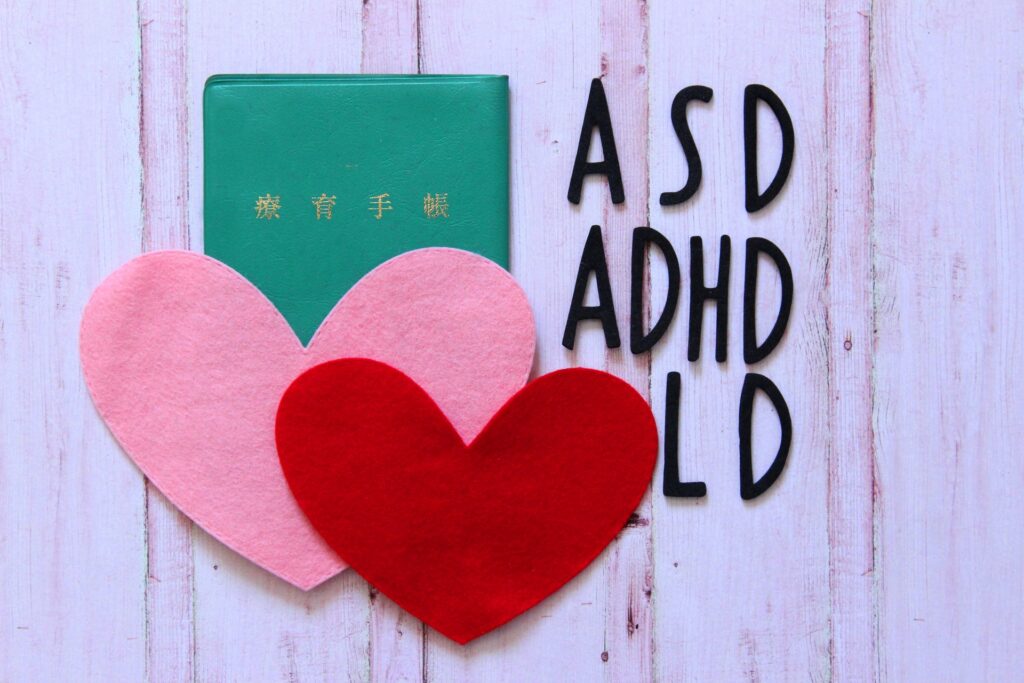
保育所等訪問支援については、「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)の中で、インクルージョン推進に重要な役割を果たすため、より効果的な活用を目指すべきとされ、人員配置や報酬の見直し、支援内容に応じた評価の検討や、保育所等の事情に左右される点への配慮、訪問支援以外の業務を含めた評価が必要とされました。また、関係者との話し合いの場の設定やICTの活用による情報共有、専門性を高めるための報酬評価の見直しも必要とされたところです。
今回は、それら指摘を踏まえ、複数の見直しが行われましたので、ご紹介します。(児童発達支援、放課後等デイサービス重複部分は除く)
1 効果的な支援の確保・促進
訪問支援時間の下限設定
まず、訪問支援時間には新たに「30分以上」という下限が設定されました。これにより、支援の質を確保し、時間不足による不十分な支援を防ぐことを目指しています。
個別支援計画の連携
また、運営基準の改正により、事業者は保育所や学校等の訪問先施設と連携して、個別支援計画の作成および見直しを行うことが求められるようになりました。
オンラインの活用
さらに、訪問先施設の職員へのフィードバックやカンファレンス、関係機関との連携の場面では、オンラインの活用が推奨されています
2 関係機関との連携の強化
保育所等訪問支援が効果的な支援を確保し、促進するためには、さまざまな関係機関との連携が重要です。例えば、訪問先の施設だけでなく、利用している児童の支援に関わる医療機関や児童相談所などとも連携することで、より充実したサポートを提供することが可能です。
これらの関係機関と協力しながら、個別支援計画の作成やケース会議を実施した場合の連携の取り組みを評価するために、新たに「関係機関連携加算」が設けられました。この加算は、関係機関との会議や情報共有が行われた場合に適用され、1回あたり150単位が支給されます。ただし、月1回を限度としています。
≪関係機関連携加算【新設】≫
関係機関連携加算 150単位/回(月1回を限度)
3 自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入
質の高い支援を提供するために、事業所に対して自己評価、保護者評価、訪問先評価の実施と公表が求められるようになりました。具体的な取り組み内容
自己評価
事業所自らが支援の質を評価し、改善のための取り組みを行います。
保護者評価
支援を受けている障害児の保護者保護者の声を反映し、より良い支援を目指すものです。
訪問先評価
訪問支援員が訪問する施設(保育所等)からの評価を受け、支援の質を確認し、改善を図ることも求められます。
これらの評価は、おおむね1年に1回以上実施し、保護者や訪問先施設に結果を示すとともに、インターネットなどを利用して広く公表することが必要です。
公表しない場合の減算措置
万が一、自己評価や保護者評価、施設評価の結果を公表しなかった場合は、報酬の減算が適用されます。具体的には、所定単位数の85%しか算定されません。この減算措置は、令和7年4月1日から適用される予定ですが、それまでの1年間は経過措置として猶予期間が設けられています。
≪自己評価結果等未公表減算【新設】≫
自己評価結果等未公表減算 所定単位数の85%を算定
4 訪問支援員特別加算の見直し
これまでの加算は、支援員を配置するだけで適用されていましたが、今後は配置だけでなく、当該職員が実際に支援を行うことが求められます。さらに、より経験のある訪問支援員に対して、加算評価も見直されました。
現行の訪問支援員特別加算
これまでは、障害児支援の業務経験が5年以上(他の職員は10年以上)の保育士、児童指導員、作業療法士などが配置された場合に、1日あたり679単位が支給されていました。
見直し後の加算内容
今回の見直しにより、訪問支援員の経験年数に応じて、加算額が以下のように変更されます。
訪問支援員特別加算(Ⅰ)
業務経験が10年以上、または保育所等訪問支援業務に5年以上従事している職員が支援を行う場合、1日あたり850単位が支給されます。
訪問支援員特別加算(Ⅱ)
業務経験が5年以上10年未満、または保育所等訪問支援業務に3年以上従事している職員が支援を行う場合、1日あたり700単位が支給されます。
5 医療的ケア児や重症心身障害児等への支援の充実
医療的ケアが必要な児童や重症心身障害児へのサポート体制が強化され、特に、重度の障害を持つ子どもたちが、適切な支援を受けながらインクルーシブな環境で過ごせるよう、評価制度が新たに設けられました。
ケアニーズ対応加算について
今回新設された「ケアニーズ対応加算」は、重症心身障害児や医療的ケアが必要な子どもたちに対する支援を評価するものです。具体的には、次の条件を満たす場合に適用されます。
加算条件
訪問支援員特別加算の対象となる職員が配置され、重度の障害を持つ子どもや医療的ケアを必要とする子どもに対して支援が行われた場合、1日あたり120単位が加算されます。
6 家族支援の充実(家庭連携加算の見直し)
家族のニーズや状況に応じた支援を強化するため、家庭連携加算が見直され、新たに「家族支援加算」が導入されました。
現行の家庭連携加算(月2回を限度)
これまでの家庭連携加算では、入所児童の家族に対して個別に相談援助を行った際、以下の条件で加算が適用されていました。
居宅訪問(1時間以上):280単位/回
居宅訪問(1時間未満):187単位/回
見直し後の家族支援加算
今回の見直しでは、個別相談支援に加えて、対面やオンラインでの支援、さらにはグループでの支援も評価対象に含まれるようになりました。具体的な加算内容は以下の通りです。
家族支援加算(Ⅰ)(月2回を限度)
<入所児童の家族に対して個別に相談援助を行った場合>
居宅訪問(1時間以上):300単位/回
居宅訪問(1時間未満):200単位/回
事業所等で対面:100単位/回
オンライン:80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)
<入所児童の家族に対してグループで相談援助を行った場合>
事業所等で対面:80単位/回
オンライン:60単位/回
※また、多機能型事業所において同一の児童が複数のサービスを受ける場合、家族支援加算(Ⅰ)および(Ⅱ)は、それぞれ月4回を超えて算定することはできません。
まとめ
以上、今回の報酬改定においては、保育所等訪問支援の質を一層向上させるために多岐にわたる見直しが実施されました。これにより、インクルージョン推進に向けた取り組みがさらに進展し、保育所等訪問支援は今後ますますその重要な役割を果たしていくことが期待されます。
↓

