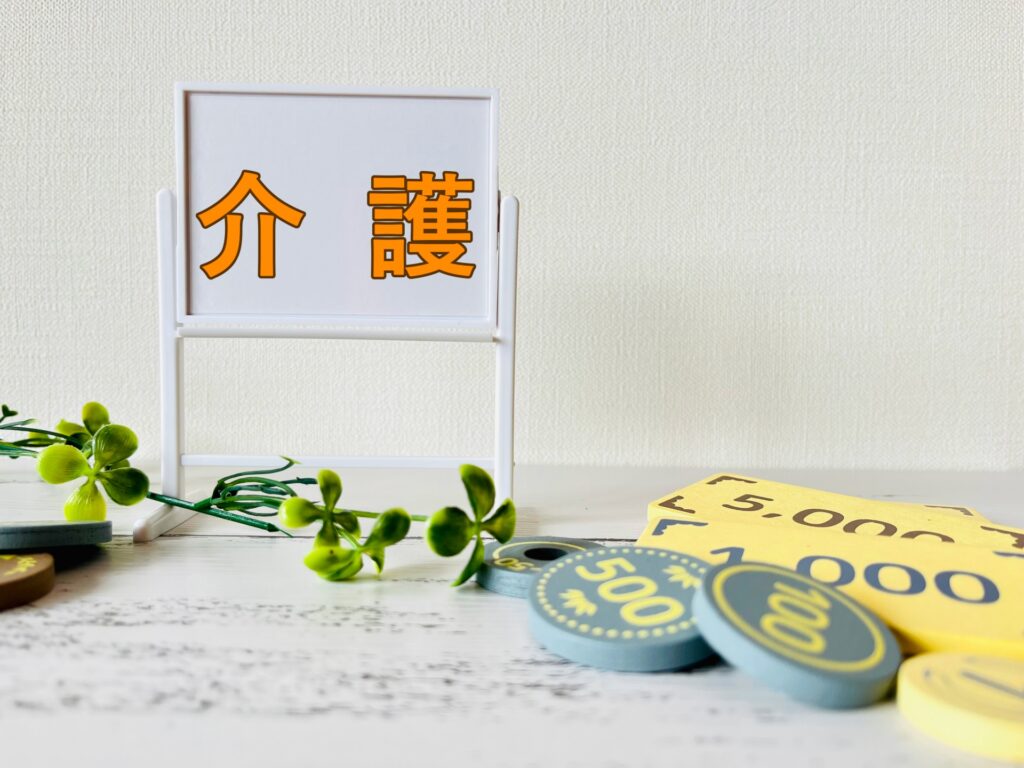
BPSDへの対応
認知症の方の尊厳を守り、本人主体の生活を支えるためには、BPSD※(認知症に伴う行動・心理症状)の発現を未然に防ぐことが非常に重要と言われてきましたが、その中でも特に、平時からの予防的な取り組みや体制整備が鍵とされてきました。
※BPSD(行動・心理症状)=認知症の患者さんに見られるさまざまな症状のこと。不安や抑うつ、幻覚、妄想、攻撃性、徘徊といった行動が含まれ、患者さんが抱える精神的な苦痛や、環境の変化、身体的な健康問題などによって引き起こされることが多い。
令和3年度からは老健事業において、BPSDの予防や再発防止に向けた評価方法や体制、実践方法などの検討が進められ、これまでの検証で日常生活の自立度と有意な相関があることが確認されています。
この結果を踏まえ、BPSDの発現を防ぐ、あるいは発現時に早期対応できる体制を強化するため、新たな加算が設けられることになりました。
認知症チームケア推進加算
【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設】
「認知症チームケア推進加算」には「認知症チームケア推進加算(Ⅰ)」と「認知症チームケア推進加算(Ⅱ)」の2つがあり、それぞれ要件を満たすことで、月ごとに150単位または120単位が算定できるようになります。
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
単位数
150単位/月
算定要件
この加算を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:
(1)利用者や入所者のうち、認知症で日常生活に対する注意を必要とする人が全体の半数以上であること。
(2)BPSDに資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了した者又は認知症介護に係る専門的な研修及びBPSD予防ケアプログラムを含む研修を修了した者を1名以上配置し、複数の介護職員で認知症対応チームを編成していること。
(3)認知症の行動・心理症状を個別かつ計画的に評価し、その結果に基づいたチームケアを実施していること。
(4)BPSDに資する認知症ケアに関するカンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評価、ケアの振り返りや計画の見直しを行うこと。
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
単位数
120単位/月
算定要件
「加算(Ⅰ)」の(1)(3)(4)の要件を満たし、BPSDに資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了した者を1名以上配置し、複数の介護職員で認知症対応チームを編成していること。
なお、「認知症専門ケア加算(Ⅰ)または(Ⅱ)」を既に算定している場合には、この新たな加算は重複して算定することができない点に注意が必要です。
この加算の背景
認知症ケアにおいては、BPSDを予防し、発現時に早期対応することが非常に重要です。今回の新設された加算は、認知症ケアの質をさらに高めるため、介護現場でのチームケアの重要性を反映しています。特に、研修を修了した専門家を配置することで、より適切な対応ができる体制を整え、定期的な評価と計画的な見直しを行うことが求められています。
BPSDへの対応は、認知症患者さんの生活の質向上に直結するため、今回の加算を活用して、現場でのケアの質をさらに高めていくことが期待されます。
以下、これまでに公表されたQ&Aについて抜粋してご紹介いたします。
Q&A VOL.2
問1「認知症チームケア推進研修(認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSD の出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修をいう)」について、研修内容はどのようなものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。
(答)研修内容は、以下に示す認知症の人へのケアに関する内容を含むものとする。
・BPSD のとらえかた
・重要なアセスメント項目
・評価尺度の理解と活用方法
・ケア計画の基本的考え方
・チームケアにおける PDCA サイクルの重要性
・チームケアにおけるチームアプローチの重要性
また、研修の実施主体は、認知症介護研究・研修センター(仙台、東京、大府)であり、全国の介護職員を対象として研修を実施する予定としているが、各都道府県・指定都市が実施主体となることや、各都道府県・指定都市が実施している認知症介護実践リーダー研修に上記の研修内容を追加して実施することは差し支えない。
なお、各都道府県・指定都市において上記の研修を認知症介護実践リーダー研修に追加して実施する場合には、認知症チームケア推進研修の研修内容が含まれた研修を修了した旨を修了証に記載するなど明確になるよう配慮されたい。
問2 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)では現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは、要件を満たさないという認識で良いか。また、認知症チームケア推進加算(Ⅱ)は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないという認識で良いか。
(答)
貴見のとおり。
本加算(Ⅰ)では、現行の認知症介護指導者養成研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了する必要がある。同様に、本加算(Ⅱ)では、認知症介護実践リーダー研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了する必要がある。
問3 本加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)が認められる入所者等にのみ加算が算定できるのか。
(答)
本加算は、BPSD の予防等に資する取組を日頃から実施していることを評価する加算であるため、本加算の対象者である「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」に対し、BPSD の予防等に資するチームケアを実施していれば、算定が可能である。
問4 本加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対応するチーム」に参加可能と考えてよいか。
(答)
貴見のとおり。
ただし、配置要件となっている者が複数のチームに参加する場合であっても、各々のチームにおいて、本加算において求められる計画の作成、BPSD の評価、カンファレンスへの参加等、一定の関与が求められる。
問5 「複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んで
いること」とあるが、介護職員とはどのような者を指すか。
(答)
本加算の対象である入所者等に対して、本加算の対象となるサービスを直接提供する職員を指す。なお、職種については介護福祉士以外であっても差し支えない。
問6 対象者に対して個別に行う認知症の行動・心理症状(BPSD)の評価は、認知症チームケア推進研修において示された評価指標を用いなければならないのか。
(答)
貴見のとおり。
問7 認知症チームケア推進加算の算定要件は、入所(居)者又は入院患者のうち認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の割合が 1/2 以上であることが求められているが、届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者等数の平均で算定するということで良いか。
(答)
貴見のとおり。
問8 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年3月 14 日厚生労働省告示第 126 号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年3月 14 日厚生労働省告示第 128 号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成 12年2月 10 日厚生省告示第 21 号)において、認知症チームケア推進加算を算定している場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算の算定が不可とされているところ、同一施設内で、入所者等 A に対しては認知症専門ケア加算、入所者等 B に対しては認知症チームケア推進加算を算定することは可能か。
(答)
可能である。
問9 問8にあるように、同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算を算定することができるのは、どのような趣旨か。
(答)
認知症チームケア推進加算は、本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求めたものではあるが、施設・事業所内の入所者等の認知症の症状は、様々であることが想定される。そのため、例えば、認知症専門ケア加算を算定している対象者が施設・事業所内に居る場合でも、認知症の症状が不安定で、認知症チームケア推進加算に基づくケア提供が、より望ましいと認められる場合は、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替えていただくことは、差し支えない。各施設・事業所においては、各加算趣旨及び各入所者等の認知症の症状に鑑み、適切な対応をお願いしたい。
問 10 「別紙様式及び介護記録等」とは具体的に何を指すか。
(答)
具体的には、下記のとおりであり、認知症チームケア推進加算算定にあたり、必ず作成が求められる。
・別紙様式:認知症チームケア推進加算に係るワークシート
・介護記録等:介護日誌や施設サービス計画書、認知症対応型共同生活介護計画書等を示す。
なお、介護記録等については、入所者等の状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返り等を丁寧に記載されることが重要であり、例示した介護記録等以外のものを使用しても差し支えないほか、この加算のみのために、新たな書式を定めることは必要ない。
Q&A VOL.6
問4 厚生労働省の令和3~5年度老人保健健康増進等事業(※)において、研修を修
了した者は、認知症チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいか。
※ 令和3年度 BPSD の軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究、令和4~5年度 BPSD の予防・軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究(実施主体:社会福祉法人浴風会)
(答)
貴見のとおり。なお、令和5年度 BPSD ケア体制づくり研修修了者でない者については、令和6年度中に速やかに、認知症チームケア推進ケア研修で用いる研修動画を視聴することが望ましい。
問5 認知症チームケア推進加算Ⅱの配置要件として、認知症介護実践リーダー研修と
認知症チームケア推進研修の双方の研修を修了した者の配置が必要とされるが、認
知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている者について、認知症介護実践リ
ーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能か。
(答)
可能である。配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等から構成するチームを組むことが、本加算の要件となっていることから、チームケアのリーダーを養成するための認知症介護実践リーダー研修の受講対象となる者は、認知症チームケア推進研修の受講対象者になるものと考える。
問6 同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア
推進加算に切り替える場合に、どのような算定方法となるのか。
(答)
当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進加算の算定要件を満たすサービスを提供しているのであれば、当該月については、認知症チームケア推進加算を算定することが可能である。ただし、この場合、認知症専門ケア加算については、算定することができない。
Q&A VOL.9
問 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)において、研修に係る算定要件は具体的にどのようなものか。
(答)
本加算の研修に係る算定要件として、本加算(Ⅰ)については、「認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了している者」としており、これは、認知症介護指導者養成研修と認知症チームケア推進研修の両方を修了した者を指している。
また、本加算(Ⅱ)については、「認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」としており、これは、認知症介護実践リーダー研修と認知症チームケア推進研修の両方を修了した者を指している。
詳細については、「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について」(令和6年老高発 0318 第1号、老認発 0318 第1号、老老発 0318 第1号通知)を御参照いただきたい。
| 区分 | 認知症チームケア推進加算Ⅰ | 認知症チームケア推進加算Ⅱ |
| 算定要件となる研修 | 認知症介護指導者養成研修 + 認知症チームケア推進研修 | 認知症介護実践リーダー研修 + 認知症チームケア推進研修 |
↓
