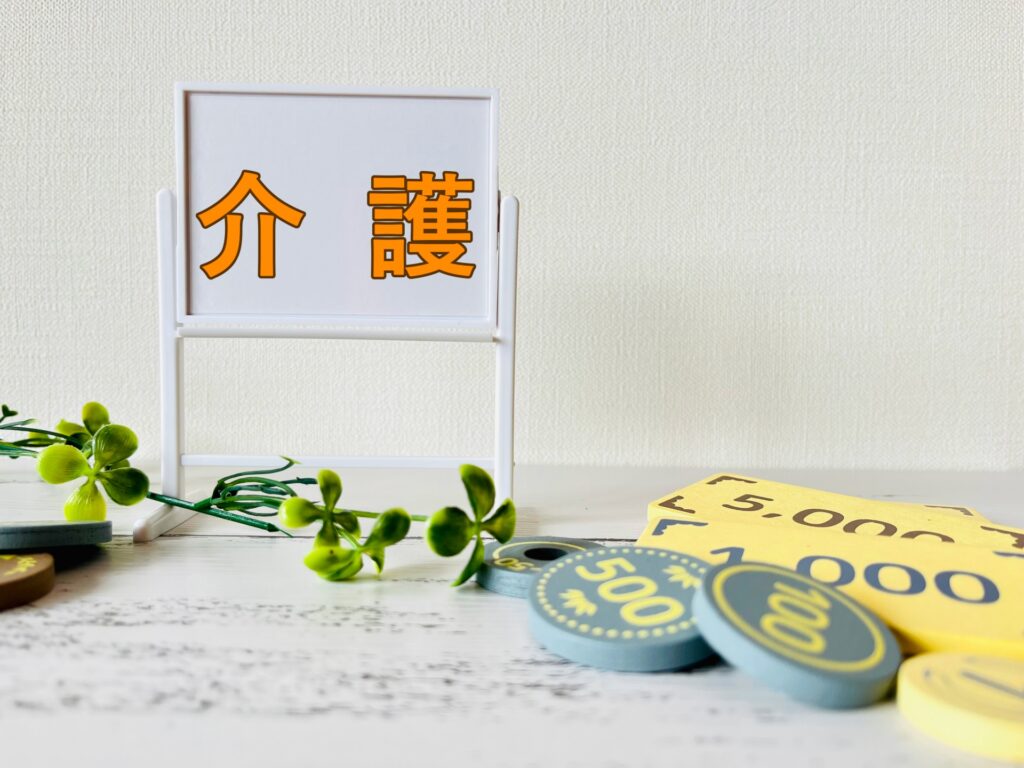
今回は、改定された通所介護施設における入浴介助加算について取り上げます。
今回の改定では、単位数について見直しは行われず、算定要件のみの見直しとなります。
なお、サービス別入浴介助加算単位数は以下のとおりです。
| サービス種別 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴介助加算(Ⅱ) |
| 通所介護 | 40単位/日 | 55単位/日 |
| 地域密着型通所介護 | ||
| 認知症対応型通所介護 | ||
| 通所リハビリテーション | 60単位/日 |
<改定に至るまでの経緯>
通所系サービスにおいて提供される入浴介助加算には、現在「Ⅰ」と「Ⅱ」の2種類があります。
入浴介助加算Ⅱの導入背景
入浴介助加算Ⅱは、利用者が自宅での入浴を自立して行えるよう支援するために、令和3年度の介護報酬改定で新設されました。
しかし、現状、この加算Ⅱはそれほど広く活用されていないのが実情となっております。
※入浴介助加算の算定状況(令和4年8月データ)
加算Ⅰの算定率について、通所介護の91.4%、地域密着型通所介護の73.9%、認知症対応型通所介護の94.9%の事業所で高い割合で算定されています。
これに対して、加算Ⅱの算定率は通所介護で12.2%、地域密着型通所介護で7.5%、認知症対応型通所介護で9.2%と非常に低い水準となってます。
加算Ⅱが利用されない理由
加算Ⅱの利用が進まない背景には、いくつかの理由が指摘されています。
医師などとの連携の困難さ
利用者の居宅を訪問して評価や助言を行う医師や専門職の確保が難しい状況にあります。
浴室環境の整備の難しさ
事業所の浴室が個浴や、利用者の自宅の浴室に近い環境を整えることが困難な場合があります。
個別入浴計画の作成の困難さ
入浴に関する事項のみを記載した単独の計画を作成することが現場では大きな負担となっていることも上げられます。
改善に向けた取り組みと周知不足
なお、国の方では、個別入浴計画については、「個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することで、個別の入浴計画の作成に代えることができる」とする通知を発出しています。
また、個浴槽についても、「個浴槽がなくても、利用者の居宅に近い環境が整備されていれば問題ない」とするQ&Aも示しています。
しかし、このことについて事業所の理解が不十分であることもあって、加算Ⅱの算定が進まない一因となっています。
加算Ⅰにおける入浴介助研修の実施状況
一方、加算Ⅰについては、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う際に算定されるものですが、入浴介助に係る従業員の研修の実施状況を見ると、通所介護では40.5%、地域密着型通所介護では35.5%、認知症対応型通所介護では38.8%の事業所が「行っていない」と回答しています。
これは、加算Ⅱを算定している事業所の研修実施率が約7割であることと比べると、低い数値です。
通所介護等における入浴介助加算について、これまでの経緯を踏まえ、以下のような見直しが行われました。
見直し内容
1 入浴介助技術の向上に向けた研修の要件化(加算Ⅰ)
まず、入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に新たな変更が加えられました。
これまでは、加算を算定するための技術的要件が中心でしたが、さらに入浴介助に関する研修の実施が必須となりました。
この変更により、入浴介助に関わる職員が定期的に研修を受け、スキルアップを図ることが求められることになりました。
この要件は、以下の通所系サービスに適用されます。
・通所介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
2 入浴介助加算(Ⅱ)の要件の緩和と明確化
次に、入浴介助加算(Ⅱ)についても見直しが行われました。
現行の算定要件では、「医師等(※)による利用者宅の浴室環境評価・助言」が求められていましたが、この要件を柔軟化し、介護職員が医師等の指示のもとで利用者の自宅を訪問し、ICT機器を活用して状況を把握する方法が導入されます。
この方法により、医師等が現地に直接訪問しなくても、ICT機器を通じたデータで評価・助言が可能となり、加算Ⅱの算定が認められるようになります。これにより、人材の有効活用が期待されています。
(※)医師等とは・・・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者
3 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件の明確化
さらに、利用者が自宅で自立した入浴を目指す取り組みを促進するため、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件について、現行のQ&Aや留意事項通知で示されている内容を、今回の改定で 正式に告示へ明記 することになりました。
この改定により、要件が明確化され、事業所が取り組みやすくなることが期待されます。
この変更は、以下のサービスに適用されます。
・通所介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリテーション
まとめ
今回の見直しは、現場での入浴介助の質を高め、利用者が自宅で自立した入浴生活を送るための支援体制を強化することを目的としています。
新たな要件に対応するための研修やICT機器の導入などが求められる一方で、人材の有効活用や要件の明確化により、現場での実践がよりスムーズになることが期待されます。
以下、これまでに公表されたQ&Aについて抜粋してご紹介します。
Q&A VOL.1
問 60 入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。
(答)
・ 具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられるが、これらに限るものではない。
・ なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。
問 61 情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。
(答)
情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらう事で要件を満たすこととしている。
問 62 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
(答)
・ 利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む。)を含む。)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。
① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作を評価する。
② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。
③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。
④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。
・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。
問 63 入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。
(答)
福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。
↓
