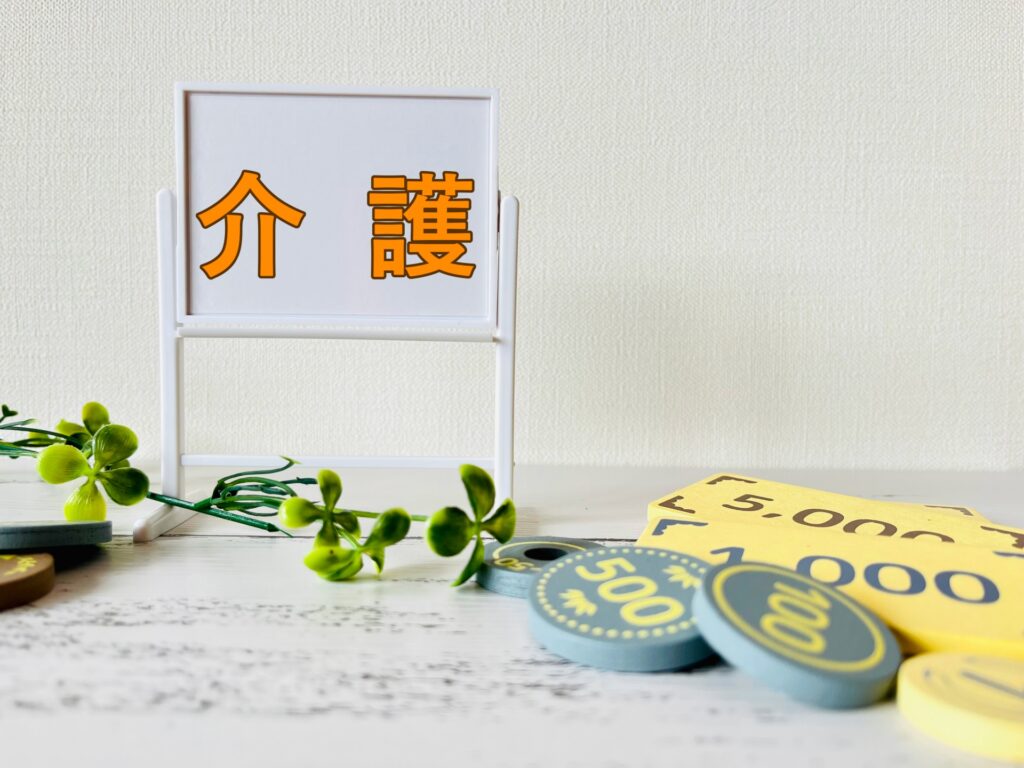
今回は、リハビリテーションマネジメント加算を取り上げます。
<現状と課題>
リハビリテーション、栄養、口腔の取組は一体となって運用されることで、重度化防止の効果がより期待されるものとして、従前よりリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進が進められてきました。
しかし、施設や通所サービスでは、歯科専門職の不足や情報共有の不十分さから、特に在宅療養者や認知症対応施設では十分な口腔ケアが行き届いていない状況が見られ、また、栄養管理についても、「栄養アセスメント加算」やスクリーニングの導入により改善が進んでいるものの、再入所時の栄養連携やリハビリと一体化した取り組みはいまだ不十分とされております。
今後もさらなる体制強化が必要とされており、介護現場では多職種連携をより強化し、より効果的なケアの実施が求められている状況です。
新しい評価基準の導入
こうした背景を踏まえ、通所リハビリテーションにおいて「リハビリテーションマネジメント加算」に新たな区分が設けられました。この区分は、口腔ケアと栄養ケアの実施をリハビリと一体化する取り組みを評価するものです。具体的には、次のような要件が含まれます。
・口腔アセスメントと栄養アセスメントを行うこと。
・リハビリ計画において、リハビリ、口腔、栄養の情報を関係職種間で一体的に共有すること。必要に応じてLIFEシステムを活用します。
・共有した情報をもとにリハビリ計画を見直し、その内容を関係職種に共有すること。
また、報酬体系の簡素化の観点から、通所および訪問リハビリテーションにおける「リハビリテーションマネジメント加算(B)」が廃止され、条件が統合されました。改定後の単位数は以下の通りです。
まず、訪問リハビリテーションからご紹介します。
訪問リハビリテーション
単位数
<改定後>
リハビリテーションマネジメント加算(イ): 180単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(ロ): 213単位/月
新設: 医師が利用者や家族に説明し、同意を得た場合に270単位/月が加算
算定要件(概要)
<リハビリテーションマネジメント加算(イ)>
この加算は、従来のリハビリテーションマネジメント加算(A)イと同じ条件で算定されます。具体的な要件は以下の通りです:
●リハビリテーション会議の開催
専門職が集まり、利用者の状況について情報を共有し、その内容を記録します。
●計画の説明と同意の取得
リハビリ計画を医師や理学療法士などが利用者や家族に説明し、同意を得ることが必要です。説明が理学療法士などによって行われた場合は、必ず医師に報告します。
●定期的な見直し
3カ月に1回以上、リハビリテーション会議を開き、利用者の状態の変化に応じて計画を見直す必要があります。
●ケアマネジャーへの情報提供
リハビリ職がリハビリに関する専門的な視点から、利用者の能力や日常生活での注意点などについて、ケアマネジャーに情報提供します。
●指導・助言の実施
リハビリ職が利用者宅を訪問し、利用者のご家族や本人、又は居宅サービスの従業者に対して、介護の工夫や日常生活でのアドバイスを行うことが求められます。
●これらの要件を満たし、すべてを記録することが必要です。
<リハビリテーションマネジメント加算(ロ)>
こちらは、リハビリテーションマネジメント加算(イ)の要件を満たした上で、さらに以下の条件をクリアする必要があります:
LIFEシステムの活用:利用者ごとのリハビリ計画書を「LIFE」に提出し、フィードバック情報を活用します。
<リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合>【新設】
さらに新設された要件として、リハビリテーション事業所の医師が利用者またはその家族に説明を行い、同意を得た場合に、月270単位が加算される制度が加わりました。
次に通所リハビリテーションです。
通所リハビリテーション
単位数
今回の改定で、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」が廃止され、名称変更と新たな加算区分が設けられました。
<リハビリテーションマネジメント加算(イ)>
同意日の属する月から6カ月以内: 560単位/月
6カ月超: 240単位/月
<リハビリテーションマネジメント加算(ロ)>
同意日の属する月から6カ月以内: 593単位/月
6カ月超: 273単位/月
<リハビリテーションマネジメント加算(ハ)>【新設】
同意日の属する月から6カ月以内: 793単位/月
6カ月超: 473単位/月算定要件
<新設された加算について>
さらに、今回新設された制度として、医師が利用者またはその家族に説明を行った場合には、上記単位に270単位が加算されます。
算定要件(概要)
<リハビリテーションマネジメント加算(イ)>
この加算は、以前の「リハビリテーションマネジメント加算(A)イ」と同じ要件が適用されます。具体的には次のような項目が求められます:
●リハビリテーション会議の開催
リハビリテーションに関する専門職が集まり、利用者の状況に関する情報を共有し、その内容を記録することが必要です。
●リハビリ計画の説明と同意の取得
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者や家族に対してリハビリ計画を説明し、同意を得ることが求められます。理学療法士などが説明を行った場合は、必ずその内容を医師に報告することが必要です。
●定期的な会議と計画の見直し
同意取得後、6カ月以内は月に1回以上、6カ月を超える場合は3カ月に1回以上のリハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じて計画を見直すことが必要です。
●ケアマネジャーへの情報提供
リハビリ職がリハビリに関する専門的な視点から、利用者の能力や自立のための支援方法、日常生活での注意点などについて、ケアマネジャーに情報を提供します。
●指導・助言の実施
リハビリ職が利用者宅を訪問し、利用者のご家族や本人、又は居宅サービスの従業者に対して、介護の工夫や日常生活でのアドバイスを行うことが求められます。
●これらの要件を満たし、すべてを記録することが必要です。
<リハビリテーションマネジメント加算(ロ)>
「リハビリテーションマネジメント加算(イ)」の要件をすべて満たしたうえで、さらに以下の条件が加わります。
●LIFEシステムの活用
利用者ごとのリハビリテーション計画書を「LIFE」に提出し、フィードバック情報を活用することが求められます。
<リハビリテーションマネジメント加算(ハ)>【新設】
新たに設けられた「加算(ハ)」では、「加算(ロ)」の要件を満たすことに加え、以下の追加要件が求められます:
●管理栄養士の配置
事業所に管理栄養士を1名以上配置しているか、外部と連携して栄養管理を行います。
●栄養アセスメントと口腔健康評価
多職種が協力して利用者の栄養状態と口腔の健康状態を評価し、必要な課題を把握することが必要です。また、言語聴覚士や歯科衛生士、看護職員などが共同で口腔の健康状態を評価し、解決すべき課題を把握します。
●情報の相互共有
関係職種がリハビリテーション計画の内容や、利用者の口腔・栄養状態に関する情報を共有し、必要に応じて計画の見直しを行い、その情報を共有します。
まとめ
今回の改定により、リハビリ、栄養管理、口腔ケアが一体的に取り組まれる体制が強化されました。特に、「リハビリテーションマネジメント加算(ハ)」が新設されたことで、多職種連携がより推進され、管理栄養士や言語聴覚士、歯科衛生士などの協力が不可欠となっています。
また、従来のリハビリテーションマネジメント加算の名称が変更され、加算の条件も統合されるなど、よりシンプルな形になりました。
今後も、現場でのフィードバックや利用者のニーズに基づき、さらに見直しが行われる可能性があります。多職種連携の強化やケアの一体化を進めるため、制度の柔軟な適応が期待されており、今後も状況に応じてさらなる改善が図られるでしょう。
以下、これまでに公表されたQ&Aについて抜粋してご紹介します。
Q&A VOL.1
問 78 リハビリテーションマネジメント加算の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
(答)
訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適時適切に実施すること。
問 80 リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定した翌月に、栄養アセスメント加算を算定する場合、LIFE へのデータ提出は必要か。
(答)
・ 利用者の状況に変化がないと判断される場合、LIFE にデータを提出する必要はない。
・ ただし、栄養アセスメントを行った日の属する月から少なくとも3月に1回は LIFEにデータを提出すること。
問 81 リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」と
あるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
(答)
・ 利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。
・ ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。
問 83 事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用している利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
(答)
・居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で実施しても差し支えない。
問 84 リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)及び(ハ)について、同一の利用者に対し、加算の算定要件の可否によって、月ごとに算定する加算を選択することは可能か。
(答)
可能である。
問 85 同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
(答)
・ それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしている場合においては、当該加算を各々算定することができる。
・ ただし、前提として、複数事業所の利用が認められるのは、単一の事業所で十分なリハビリテーションの提供ができない等の事情がある場合であり、適切な提供となっているかは十分留意すること。
・ 単一の事業所で十分なリハビリテーションの提供ができない場合とは、理学療法・作業療法の提供を行っている事業所において、言語聴覚士の配置がないため、言語聴覚療法に関しては別の事業所において提供されるケース等が考えられる。
問 86 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定を新たに開始することは可能か。
(答)
・ 可能である。
・ なお、通所リハビリテーションの利用開始時に利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えた後にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(Ⅱ)を算定する。
問 87 リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(1)をそれぞれ算定している場合において、同意を得た日から6ヶ月が経過していない時点で、月1回のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断した場合、3月に1回のリハビリテーション会議の開催をもって、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)をそれぞれ算定することは可能か。
(答)
・ リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)については、利用者の状態が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリテーションの管理を行うことを評価するものである。したがって、利用者の同意を得た月から6月が経過していない時点で、会議の開催頻度を減らし、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)を算定することはできない。
問 88 リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
(答)
・ 取得できる。
・ リハビリテーションマネジメント加算は、「通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。
問 91 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
(答)
様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。
Q&A VOL.5
問2 リハビリテーションマネジメント加算を算定する際、リハビリテーション計画について、リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき 270 単位が加算できるとされている。医師による説明があった月のみ、270 単位が加算されるのか。
(答)
・ リハビリテーションの基本報酬の算定の際、3月に1回以上の医師の診療及び3月に1回以上のリハビリテーション計画の見直しを求めていることから、3月に1回以上、リハビリテーション計画について医師が説明を行っていれば、リハビリテーションマネジメント加算に、毎月 270 単位を加算することができる。
Q&A VOL.7
問2 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取組について、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算のⅠ、理学療法の注7、作業療法の注7、言語聴覚療法の注5、個別機能訓練加算のⅢ及びリハビリテーションマネジメント加算のハにより評価されているが、当該加算を算定する場合の科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出方法如何。
(答)
・ LIFE へのデータ提出は、介護記録ソフト等を使用して作成した CSV ファイルを用いたインポート機能を使用するか、LIFE 上での直接入力を行うこととなる。
なお、下記に記載の左欄の加算を算定する場合に、右欄の様式に対応するデータを提出することに留意する。
<加算名>
リハビリテーションマネジメント加算のハ
<データ提出に対応する様式>
・別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)
・別紙様式4-3-1(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)(様式例))
・別紙様式6-4(口腔機能向上サービスに関する計画書)のうち、「1 口腔の健康状態の評価・再評価(口腔に関する問題点等)」の各項目
↓
